土地を売却する際はさまざまな税金がかかります。
中でも、高額となる可能性があるものに、譲渡所得税とこれとセットで課される住民税が挙げられます。
では、土地の売却でかかる住民税とは、どのような税金なのでしょうか?
また、住民税と譲渡所得税はどのように算定するのでしょうか?
今回は、土地の売却でかかる住民税について詳しく解説します。
土地の売却でかかる住民税とは
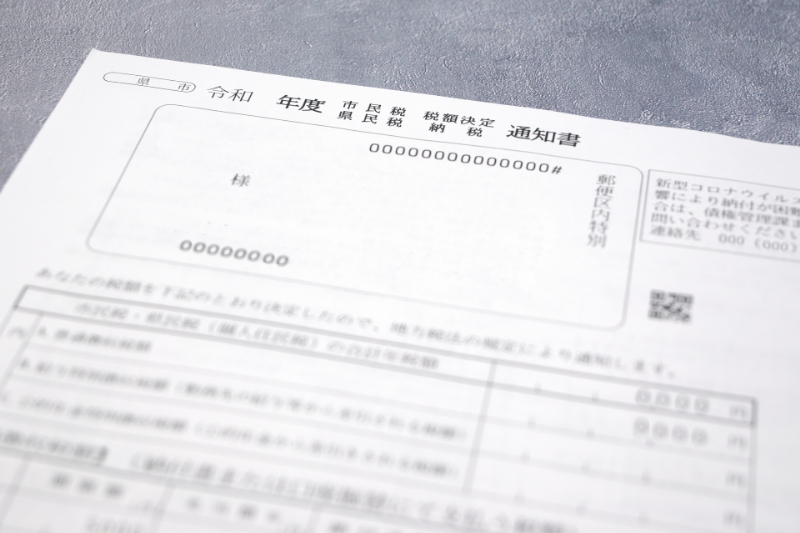
住民税とは、都道府県民税と市町村民税の総称です。
税金は大きく分けて「国に納める国税」と、「都道府県や市町村に納める住民税」があります。
土地を売却して譲渡益が出るとこの譲渡益に対して譲渡所得税がかかりますが、この譲渡所得税は国に納める国税です。
そして、譲渡所得税がかかる場合は、これと併せて住民税が課されることとなっています。
つまり、土地の売却でかかる住民税とは、土地の売却益が出た場合に国税である譲渡所得税とセットで課される税金ということです。
土地を売却する場合の譲渡所得税や住民税は高額となることもあるため、土地の査定額がわかった時点で税理士などの専門家へ相談のうえ試算してもらうようにしてください。
土地の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」を活用ください。
おうちクラベルとは、査定依頼フォームに情報を1度入力するだけで複数の不動産会社にまとめて査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。
複数社による査定額を比較することで、その土地の売却適正額が把握しやすくなり、譲渡所得税や住民税の試算もしやすくなります。
土地の売却でかかる住民税の概要
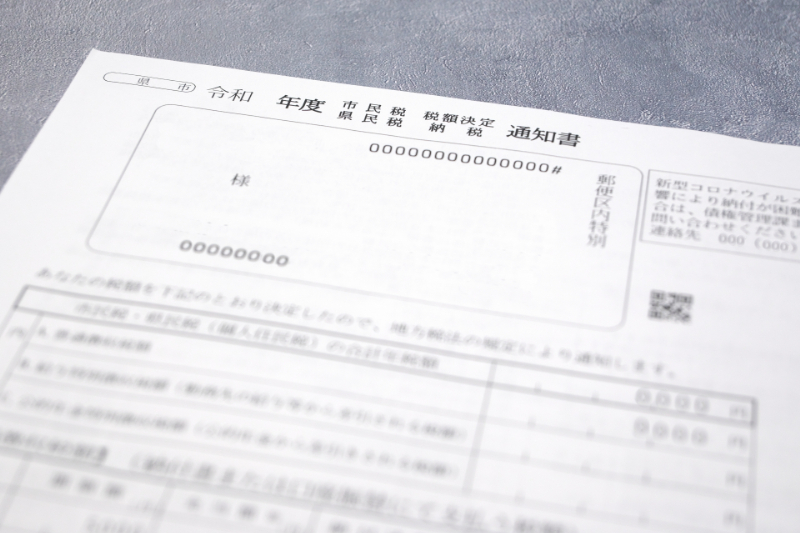
続いて、土地の売却でかかる住民税について、概要を解説します。
住民税自体の確定申告は必要ない
土地の売却益に対して住民税がかかるとはいえ、住民税自体の確定申告は必要ありません。
土地の売却で譲渡益が出たら、譲渡所得税の申告は必要となります。
譲渡所得税の申告期限は、土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。
住民税は、申告した譲渡所得税を基礎として自動的に算定のうえ課税されます。
住民税の納め方には2種類がある
住民税は「土地の売却に係る住民税」だけが単独で請求されるのではなく、給与所得や事業所得など他の所得に係る住民税と併せて課税されます。
住民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
普通徴収とは、納付書を使って自分で納付する方法です。
自営業者や専業主婦(主夫)などは、原則としてこちらとなります。
一方、特別徴収とは給与や年金から自動的に住民税が天引きされる納税方法です。
会社員や年金受給者などの場合は、原則としてこちらの方法で徴収されます。
例外として確定申告書の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選択すると、土地の売却に係る住民税を普通徴収にすることができます。
土地の売却で利益を得たことを会社の人間に知られたくない場合には「自分で納付」を選択するとよいでしょう。
住民税は翌年に納付する
土地の売却益にかかる譲渡所得税の納税期限は、申告期限と同じく土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。
一方で、これに係る住民税は普通徴収の場合、売却した年の翌年の6月頃に一括で納付する方法と、これ以後4回に分けて納付する方法の2択となります。
また、特別徴収の場合は売却年の翌年6月から翌々年の5月にかけて天引きされます。
住民税は譲渡所得税よりも後で納税することとなるため、納税資金を残しておくよう注意が必要です。
土地の売却でかかる住民税の計算方法
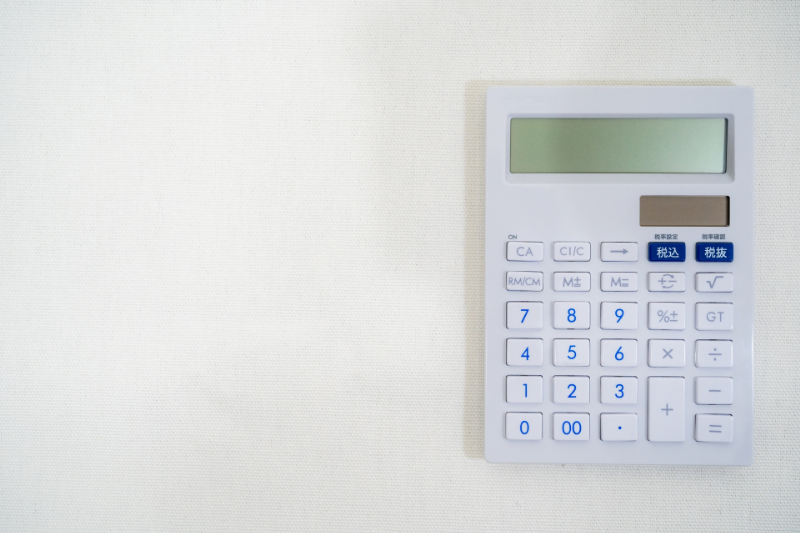
土地の売却でかかる住民税は、次の式で算定されます。
- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 住民税額=課税譲渡所得金額×税率
実際には納税者が自ら住民税を算定するのではなく、譲渡所得税額を計算するために「課税譲渡所得金額」を計算します。
確定申告書に記載した課税譲渡所得金額をもとに、自動的に住民税が算定されることとなります。
参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)
ここでは、順を追って計算の流れを解説します。
- 収入金額を算定する
- 取得費を算定する
- 譲渡費用を算定する
- 譲渡益が出たかどうかを確認する
- 特別控除を適用する
- 税率を乗じる
収入金額を算定する
最初に、「収入金額」を算定します。
収入金額とは、土地を売却したことによって買主から受け取った対価です。
この収入金額がわかると、譲渡所得税や住民税の試算がしやすくなることから、土地の査定額がわかった時点で譲渡所得税や住民税を試算しておくようにしてください。
査定には、不動産一括査定である「おうちクラベル」を活用ください。
取得費を算定する
次に、土地の取得などに要した費用である「取得費」を計算します。
取得費に計上することができるのは、原則として次の費用などです。
- 売却した土地の購入代金、改良費
- 購入手数料
- 土地を取得(購入、贈与、相続など)したときに納めた登録免許税、登記費用、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
- 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
- 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
- 土地の取得に際して支払った土地の測量費
- 所有権などを確保するために要した訴訟費用(ただし、相続争いの解決費用を除く)
- 建物付の土地を購入してその後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
- 土地を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
- 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
ただし、土地の取得費のわかる資料が残っていない場合は、「収入金額×5%」で取得費を算定することとなります。
譲渡費用を算定する
次に、「譲渡費用」を計算します。
譲渡費用とは、土地を売却するために直接かかった費用です。
譲渡費用に算入できるのは、次の費用などです。
- 土地を売るために支払った仲介手数料
- 印紙税で売主が負担したもの
- 土地を売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
- 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
一方で、売却までに負担した土地の固定資産税や、売却代金の取り立てに要した費用などは譲渡費用とはなりません。
これらは売却のために直接かかった費用とまではいえないためです。
譲渡益が出たかどうかを確認する
ここまでの結果を踏まえて、次の計算結果がプラスであるかマイナスであるかを確認します。
- 収入金額-(取得費+譲渡費用)
マイナスである場合は譲渡損が生じているためこれ以降の計算を行う必要はなく、譲渡所得税の申告や納税の義務はありません。
ただし、売却した土地がマイホームの敷地であった場合、一定の要件を満たすことで、他の所得に係る所得税が安くなる特例の適用を受けられる可能性はあります。
一方で、計算結果がプラスとなった場合は、この先の計算へと進みます。
特別控除を適用する
特別控除とは、一定の要件を満たすことで適用を受けられる、実際の支出を伴わない控除です。
土地の売却で適用を受けられる可能性がある特別控除については、後ほど解説します。
税率を乗じる
ここまでの計算結果をもとに、課税譲渡所得金額を算出します。
- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
これに対して税率を乗じることで、土地の売却でかかる住民税額が算定できます。
土地の売却益にかかる住民税の税率は売却した年の1月1日時点における所有期間に応じて異なっており、それぞれ次のとおりです。
| 売却年1月1日時点における所有期間 | 住民税の税率 |
|---|---|
| 5年超(長期譲渡所得) | 5% |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 9% |
土地を売却する際の住民税を安くする方法
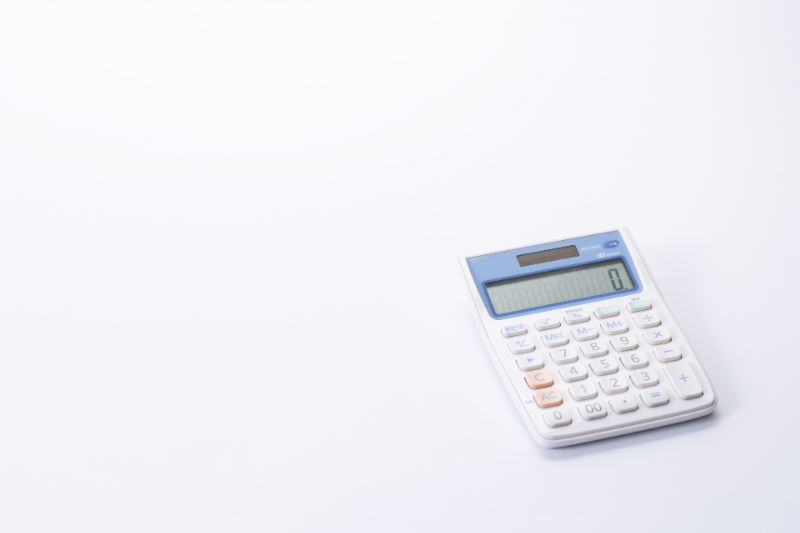
土地を売却する際の住民税を安くしたい場合、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、住民税を安くする主な方法を解説します。
- 特別控除の適用を受ける
- 特別控除以外の特例の適用を受ける
- ふるさと納税を活用する
特別控除の適用を受ける
1つ目は、特別控除の適用を受けることです。
土地の売却で使える特別控除には、次のものなどが挙げられます(いずれも国税庁参照)。
- マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除
- 収用等により土地建物を売ったときの5,000万円特別控除
- 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得100万円特別控除
ただし、特別控除にはそれぞれ厳格な要件が設けられており、1つでも要件から外れると適用を受けることができません。
また、他の特例と併用できないものが多いため、適用を受ける際は慎重な検討が必要です。
そのため、土地の査定額がわかった時点で税理士などの専門家へ相談し、特例適用について確認しておくようにしてください。
土地の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」を活用ください。
特別控除以外の特例の適用を受ける
2つ目は、特別控除以外の特例の適用を受けることです。
売却した土地がマイホームの敷地であり、その年1月1日時点における所有期間が10年超であった場合は、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を受けられる可能性があります。
この特例の適用を受けることで、土地の売却に係る住民税率が次のとおりとなります。
| 課税長期譲渡所得金額(=A) | 住民税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | A×4% |
| 6,000万円超の部分 | A×5%-60万円 |
ふるさと納税を活用する
3つ目は、ふるさと納税を活用することです。
ふるさと納税とは、地方自治体に寄附をすることで寄附金額から2,000円を控除した額について税額控除を受けられることに加え、自治体独自の返礼品を受け取れる制度です。
土地の売却によって住民税額が増える場合は、ふるさと納税による控除上限額も高くなります。
そのため、土地の売却によって住民税額が増える場合は、ふるさと納税の活用も検討するとよいでしょう。
土地の売却でかかる住民税以外の税金

土地の売却では、住民税以外にもさまざまな税金がかかります。
ここでは、土地を売却する際にかかる住民税以外の主な税金について解説します。
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税
譲渡所得税
譲渡所得税とは、土地の売却益にかかる税金です。
先ほども解説したように、土地の売却にかかる住民税は、申告をした譲渡所得税の「課税譲渡所得金額をベースとして算定されます。
譲渡所得税は、次の式で算定されます。
計算要素の内容は、先ほど解説した住民税の計算要素と同じです。
- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率
税率は、売却年1月1日時点における所有期間に応じて、それぞれ次のとおりです。
ただし、2037年までは、所得税率の2.1%にあたる復興特別所得税が加算されています。
| 売却年1月1日時点における所有期間 | 所得税の税率 (復興特別所得税を含む) |
|---|---|
| 5年超(長期譲渡所得) | 15.315% |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30.63% |
土地の売却による収入金額が分かると譲渡所得税が計算しやすくなるため、土地の査定額が分かった時点で住民税と併せて試算しておくようにしてください。
査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」を活用ください。
印紙税
印紙税とは、契約書など一定の文書に対して課される税金です。
土地の売買契約書も印紙税の課税対象であり、売買契約書には税額分の「収入印紙」を貼付しなければなりません。
印紙税額は、契約書に記載した土地の売買金額に応じ、それぞれ次のとおりです。
なお、2024年3月31日までに作成する契約書では軽減税率が適用されています。
| 契約金額 (マンションの売買価格) | 本則税率 | 軽減税率 (2024年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
土地の売買契約書を2通作成する際は、売主と買主がそれぞれ、自身の保管する契約書に貼付する分の印紙税を負担することが一般的です。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記などに対してかかる税金です。
売買による土地の名義変更にも登録免許税がかかりますが、これは買主が負担することが一般的です。
一方で、売却する土地に「抵当権」が付いている場合、この抵当権の抹消登記にかかる登録免許税は原則として売主が負担します。
抵当権とは、ローンの返済が滞った際に金融機関がその土地を競売(けいばい)にかけ、そこからローン残債を回収するための担保です。
売却しようとする土地に抵当権が付いている場合、遅くとも買主への引き渡し時点までには抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権の抹消にかかる登録免許税は、土地1筆あたり1,000円です。
抵当権の抹消手続きを司法書士に手続きを依頼する場合は、別途1万円から2万円程度の報酬が発生します。
土地の売却でかかる住民税と譲渡所得税の計算例

土地の売却でかかる譲渡所得税と住民税は、具体的にどのように算定するのでしょうか?
最後に、次の前提で譲渡所得税と住民税の計算例を紹介します。
- 土地の取得費:2,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 長期・短期の別:長期譲渡所得に該当
- その他:特例の適用は受けない
なお、土地の売却による収入金額が分かると、譲渡所得税や住民税の試算がしやすくなります。
そのため、土地の査定額がわかった時点で譲渡所得税等を試算しておくようにしてください。
土地の売却査定には、不動産一括査定である「おうちクラベル」を活用ください。
1,500万円で売却した場合
先ほどの前提条件において土地を1,500万円で売却する場合、譲渡所得税と住民税はゼロとなります。
計算過程は、次のとおりです。
- 課税譲渡所得金額:1,500万円-(2,000万円+200万円)<0 ∴0円
課税譲渡所得金額がゼロとなるため譲渡所得税等は発生せず、確定申告の義務もありません。
3,000万円で売却した場合
先ほどの前提条件において土地を3,000万円で売却する場合、譲渡所得税と住民税は162万5,200円となります。
計算過程は次のとおりです。
- 課税譲渡所得金額:3,000万円-(2,000万円+200万円)=800万円
- 譲渡所得税(復興特別所得税を含む):800万円×15.315%=122万5,200円
- 住民税:800万円×5%=40万円
- 譲渡所得税と住民税の合計額:122万5,200円+40万円=162万5,200円
5,000万円で売却した場合
前提条件のもと、土地を5,000万円で売却する場合、譲渡所得税と住民税は568万8,200円となります。
計算過程は次のとおりです。
- 課税譲渡所得金額:5,000万円-(2,000万円+200万円)=2,800万円
- 譲渡所得税(復興特別所得税を含む):2,800万円×15.315%=428万8,200円
- 住民税:2,800万円×5%=140万円
- 譲渡所得税と住民税の合計額:428万8,200円+140万円=568万8,200円
まとめ
土地を売却して譲渡益が出ると、この譲渡益に対して譲渡所得税や住民税がかかります。
譲渡所得税と住民税は高額となることも多い一方で、特別控除などの適用を受けることで税額を大きく軽減できることも少なくありません。
そのため、土地を売却する際は土地の査定額がわかった時点で特別控除が適用できるかどうかを確認し、譲渡所得税や住民税がいくらかかるのか試算しておくようにしてください。
土地の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」を活用ください。
おうちクラベルとは、査定依頼フォームに売却したい土地の情報などを1度入力するだけで、複数の不動産会社にまとめて査定の依頼ができる不動産一括査定です。
複数社による査定額を比較することでその土地の売却価格がより正確に把握でき住民税額などの試算がしやすくなるほか、より高値でその土地を売却してくれる不動産会社を見つけやすくなります。












