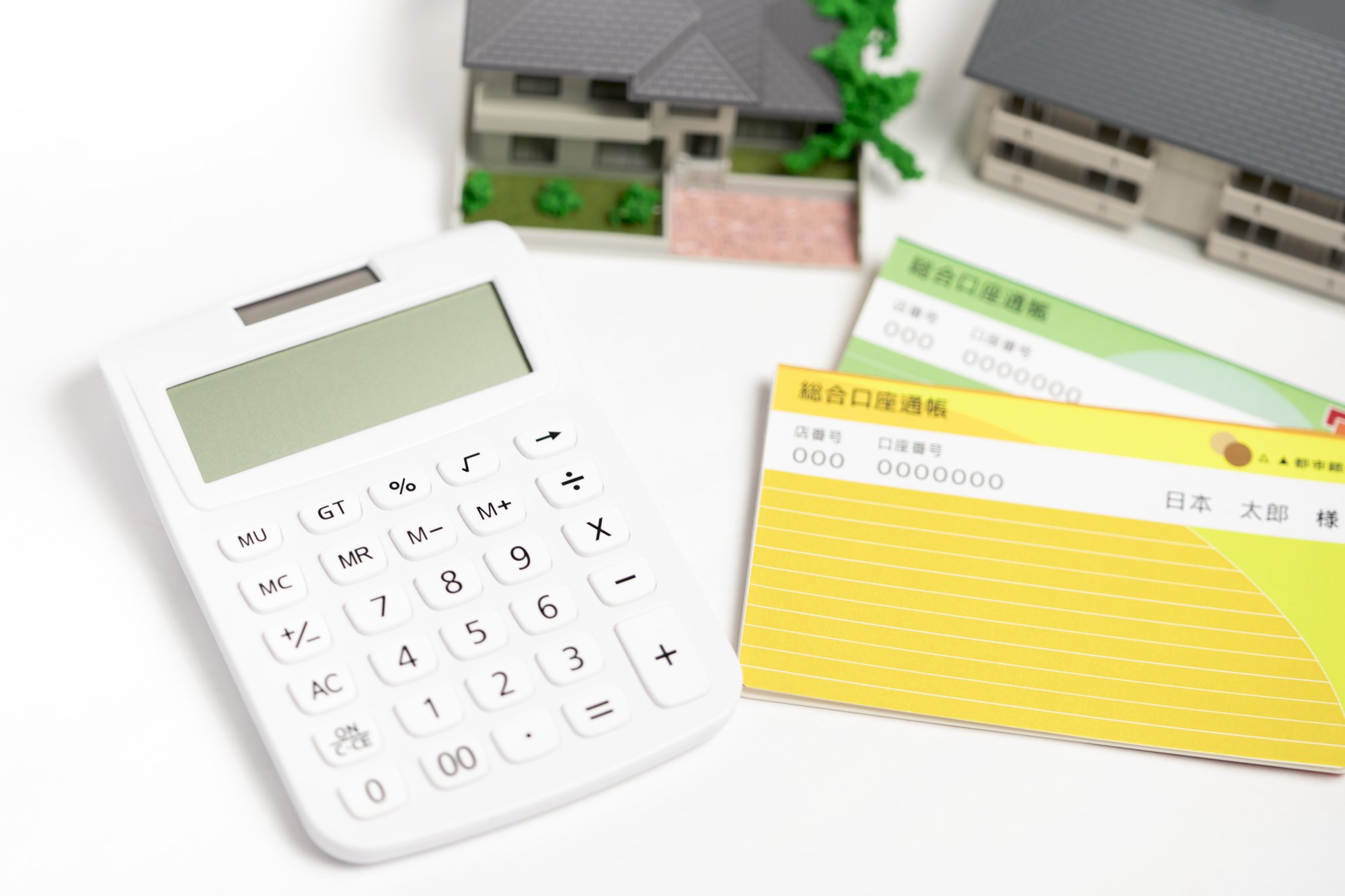家を売った時にかかる税金の種類には、印紙税・消費税・登録免許税・住民税・復興特別所得税・譲渡所得税などがあります。
ここでは、その中でも譲渡所得税についていくつかのパターンを中心に解説し、シミュレーションで具体的な事例の計算方法と税額を紹介します。
家を売った時にかかる税金とは?

マイホームを売却した時には、必ず課税される税金と必ずしも課税されない税金があります。下記の表をご参照ください。
| 税の種別 | 税の解説 | |
|---|---|---|
| 必須 | 印紙税 | 収入印紙、売買契約書に貼付 |
| 必須 | 消費税 | 仲介手数料に課税 |
| 必須でない | 登録免許税 | 登記印紙、不動産登記申請書に貼付 |
| 必須でない | 所得税 | 売却益がある時に限り課税 |
| 必須でない | 住民税 | 売却益がある時に限り課税 |
| 必須でない | 復興特別税 | 売却益がある時に限り課税 |
以下で、個別に解説していきます。
家を売った時に必ずかかる税金
(1) 印紙税
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について、印紙税の税額が軽減されています。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 200円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
引用:国税庁
たとえば、4,000万円のマンションの売買契約書には、1万円の収入印紙を貼ります。
不動産取引の慣行上は、売買契約書は2通作成し売り主と買い主の双方が各1部ずつを手元に備え置きますが、その各々の契約書に自己負担で収入印紙を貼付します。
(2) 消費税
商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税金で、仲介業者を介しての不動産売買取引の場合は、仲介手数料に課税されます。
家を売った時に場合によってかかる税金
続いて、場合によってかかる税金を説明します。
登録免許税
登記を行う者が国に納める税金で、登記申請書に登記印紙を貼付して納めます。
売買による所有権移転に関する不動産登記の場合は、新しい所有者がその登記印紙の費用を負担します。これは不動産取引の慣行です。
| 登記の種類 | 税率 |
|---|---|
| 土地の所有権移転登記申請(売買による移転) | 1.5 % ※1 |
| 土地の所有権移転登記申請(相続による移転) | 0.4 % |
| 建物の所有権保存登記申請(新築建物を取得) | 0.4 % |
| 建物の所有権移転登記申請(中古建物の売買による移転) | 2.0 % |
| 建物の所有権移転登記申請(相続による移転) | 0.4 % |
※1:令和5年3月31日まで
不動産の固定資産税評価額に上記税率を掛けて算出した金額分の登記印紙を貼ります。たとえば、固定資産税評価額が4,000万円の土地を売買で取得した時の、売買による所有権移転登記申請書には、60万円分の登記印紙を貼ります。
計算方法は下記をご参照ください。
4,000万円(固定資産税評価額)×1.5%※1=60万円(登録免許税額)
その土地の上の固定資産税評価額が1,500万円の建物を売買で取得した時には、次の通りです。
1,500万円(固定資産税評価額)×2.0%=30万円(登録免許税額)
合計で90万円分の登記印紙を各々の登記申請書に貼って納税します。
なお、固定資産税評価は各市町村が算定しており、3年に1度見直されます。評価の基準は、公示価格(不動産取引の実勢価格相当)の約70%、建物の評価額は再建築価格の約60%といわれています。
所得税
個人の所得に対して課税され、所得が多くなるほど税率が高くなります(累進税率)。
1年間のすべての所得金額から当てはまる所得控除を差し引いた、残りの課税所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
不動産の売却益に対する所得税は、譲渡所得税です。
住民税
住んでいる市区町村に納める税金で前年の収入額によって決まります。
不動産を売却する時に課される住民税は、不動産の所有期間によって2種類に分かれます。
復興特別所得税
東日本大震災の復興のためにさまざまな施策を実施するのに必要な財源を確保するために創られました。
2013年から2037年までの各年の基準所得税額が復興特別所得税の課税対象になります。
譲渡所得税の計算方法

不動産を売却した時の売却益に課される譲渡所得税も住民税と同様に、不動産の所有期間によって2種類に分かれます。
不動産の譲渡所得税率を使って譲渡所得税を算出してみましょう。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得税
土地や建物を売却した時の譲渡所得に対する税金は、売却価格から不動産の取得費や譲渡費用を差し引いたものに、所有期間に応じた税率を掛けて算出します。
取得費
土地や建物の購入代金・購入手数料・取得後の改良設備費を含み、建物の場合は減価償却費相当額を差し引きます。取得当時の売買契約書や領収書を無くして取得費が分からなくなったり、取得費が売却価格の5%に満たなかったりする場合には、取得費は売却価格の5%とみなします。
譲渡費用
土地や建物を売却するのに捻出した費用で、仲介手数料・売買契約書に貼る収入印紙代・測量費・立ち退き料・取り壊し費用などです。
仮に、取得費:1,000万円、譲渡費用:100万円、売却価格:5,000万円、特別控除:3,000万円とすると、譲渡所得税の算出の基礎となる課税譲渡所得額はこのようになります。
課税譲渡所得
=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
=5,000万円-(1,000万円+100万円)-3,000万円
=900万円
譲渡所得税の計算方法
この場合の譲渡所得税額は、下記の通りです。
- 所得税: 900万円×15%=135万円
- 住民税: 900万円×5% =45万円
- 復興特別消費税:135万円×2.1%=2万8,350円
(1)+(2)+(3) =135万円+45万円+2万8,350円=182万8,350円となります。
これは売却益が3,000万円以上の場合であって、売却益が少ない又は売却損がでた場合には課税されません。
譲渡所得税の早見表
不動産の所有期間によって短期譲渡所得、長期譲渡所得に分類され別々の税率が課されます。分かりやすくまとめた税金早見表をご紹介します。
・長期譲渡所得と短期譲渡所得
長期・短期の判定は、不動産を売却した年の1月1日時点で5年あるかないかによります。
復興特別所得税率(2.1%)は2037年までとし、所得税額に乗じて算出します。
家を売った時の税金に適用できる特例や特別控除

要件によって特例や特別控除があり、いずれも税金を安くする働きがあります。
長期譲渡所得税・短期譲渡所得税の課税は利益があることが要件となっていて、さらに利益から3,000万円を控除して、それでも利益が残ればそこに課税するというものです。
マイホームで3,000万円以上の利益がでることは多くないため、マイホームのほとんどのケースが実質非課税になることが多いのです。3,000万円の特別控除については詳しく後述します。
マイホームに関する税金には多くの特例や優遇措置が用意されており、これらのことを知っていればお得な時期に不動産の売却をするなどの立ち回りが可能となります。
3,000万円の特別控除の特例
マイホームを売却した時には、所有期間の長さに関わらず、譲渡所得益から最高で3,000万円まで控除できる特例があります。
特例を受けるための適用要件は以下の通りです。
(1)自らが住む家を売却するか、家とともに敷地や借地権を売却すること。
今は住んでいないが以前に住んでいた家や土地の場合は、住まなくなった日から3年以内の年の12月31日までに売却する必要があります。
住まなくなって解体した場合には、次の要件が加わります。
・その敷地の売買契約が家を解体した日から1年以内に締結されて、住まなくなった日から3年以内の12月31日までに売却すること。
・家を解体してから売買契約を締結した日まで、その土地を別の用途(貸し駐車場など)として使っていないこと。
(2)売却した年の1年前又は2年前に「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によってこの特例の適用を受けている場合を除く、又はマイホームの譲渡損失についての損益通算や繰越控除の特例を受けていないこと。
(3)売却した年や、その1年前から2年前にマイホームの買換えの特例を受けていないこと。
(4)売却した家や土地が、収用等の特別控除や他の特例を受けていないこと。
(5)災害で壊れた家は、住まなくなった日から3年以内の年の12月31日までに、その土地を売却すること。
(6)売り主と買い主が、親子や夫婦でないこと。
この他生計を一にする親族や家を売却したあともその家で同居する家族、内縁関係人なども含みます。
なお、特例を適用するには確定申告が必要です。
マイホームの所有期間が10年を超える場合の軽減税率の特例
土地や建物を売却して得た所得は、他の給与所得等とは分けて計算されます。その際に長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって適用する税率が異なり、不動産の所有期間に応じた税率を使い分けて計算します。
前述の譲渡所得税の計算では、不動産を長期間保有していたものとして、長期譲渡所得税率を使って算出しました。
土地や建物を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているなら「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」に分類します。
たとえば、2021年に売却した場合には、その土地や建物を取得したのが2015年12月31日以前なら「長期譲渡所得」に、2016年1月1日以後なら「短期譲渡所得」ということです。
マイホームの売却で損失がでた場合に所得から損失を控除できる
マイホームを売却して譲渡益がでた場合には特別控除などの特例がありましたが、譲渡損失がある場合には、損益通算や繰越控除をして所得税や住民税を節税できる特例があります。
マイホームを売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失(売却によってでた損失)が生じた場合には、次の(1)・(2)によってその譲渡損失をその年の他の所得と損益通算(所得と損失を相殺)することができます。
もしもその年で通算しきれない譲渡損失があった場合には、その年の翌年以後3年以内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年の分は除く)の所得から繰越した控除分を再度差し引くことができます。
(1)新たにマイホームを買換える場合
マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間で新たなマイホームを購入して、その年末に新たなマイホームの住宅ローンに残高があるなど、一定の要件がある場合に、売却したマイホームの譲渡損失について、損益通算や繰越控除をすることができます。
(2)新たにマイホームを買換えない場合
マイホームの売買契約締結日の前日に住宅ローンの残高があるマイホームを売却した場合など一定の要件がある場合は、そのマイホームの譲渡損失(ただし住宅ローンの残高からマイホームの売買金額を控除した残額を上限とする)の金額について、損益通算や繰越控除ができます。
家を売った時にかかる税金の注意点

マイホームを売却した時にかかる税金についてまとめました。
(1)印紙税
売買契約書に貼る収入印紙で、買い主・売り主双方とも自己負担で自分の契約書に貼ります。契約書記載の金額が1,000万円を超えて5,000万円以下なら、1万円の収入印紙です。
(2)消費税
不動産会社への仲介手数料にかかる消費税です。5,000万円の物件の最大仲介手数料は156万円、加えて消費税は15万6,000円です。なお、不動産登記を依頼する司法書士の報酬に対しても消費税がかかります。
(3)登録免許税
不動産登記申請には登記印紙を貼付します。売却の際の抵当権抹消登記は土地と建物と2物件なら、1,000円×2件=2,000円です。
(4)譲渡所得税
所有期間が5年を超えるか超えないかで、税額を算出する時の税率を使い分けます。マイホームを5年を超える長期にわたって保有していて売却した場合には、課税譲渡所得金額に所得税率15.315%を掛けて算出します。
(5)住民税
所有期間が5年を超えるか超えないかで、税額を算出する時の税率を使い分けます。マイホームを5年を超える長期にわたって保有していて売却した場合には、課税譲渡所得金額に住民税率5%を掛けて算出します。
(6)復興特別所得税
マイホームを5年を超える長期にわたって保有していて売却した場合には、2037年までは復興特別所得税として基準所得税額の2.1%を掛けて算出します。
新居購入時の住宅ローン減税と売却時に使用できる特例は併用できない
住宅ローン減税と併用できない特例を3つご紹介します。
(1)3,000万円の特別控除の特例
マイホーム売却による売却益から3,000万円を控除してくれる特例。ほとんどのマイホーム売却の場合で譲渡所得税を非課税にできる制度です。
(2)所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分は通常の税率20.315%→14.21%が適用できます。
(1)の3,000万円の特別控除の特例とは併用できません。
(3)特定の居住用財産の買換え特例
マイホームを買換える際の売却益に対する課税を次回のマイホーム売却時まで先送りにできる制度です。
ただし、マイホームの売却によって損失がでた場合の「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は住宅ローン控除と併用ができます。
つまり、上記(1)(2)(3)のように、マイホーム売却で利益がでているなら住宅ローン減税とは併用できず、損失がでているなら併用やむなしという意味合いです。
税金以外に注意が必要
マイホームの売却時に場合によっては必要になる、税金以外の費用もご紹介します。
(1)売却に関わった不動産会社への仲介手数料
マイホームの斡旋から条件交渉と売買契約そして引き渡しまで不動産会社に任せます。
仲介手数料の上限額は、400万円を超える不動産の場合で、3%+6万円+消費税です。
(2)司法書士への報酬
不動産登記申請の代行業務と残金決済の立ち会いなどの費用。
(3)測量・土地の造成費用
土地の測量や境界標の復元や隣地境界確定などが必要なら、土地家屋調査士の費用。
造成などが必要ならその工事費用。
(4)リフォーム費用
売却の前提や売却の条件としてリフォームが必要ならその費用。
(5)撤去・取り壊し・廃棄処分の費用
不要なものの撤去・付帯する小屋などの解体・それらの処分などの費用。
家を売却したら翌年に確定申告をする必要がある
次の3つについて、特例を受ける場合には確定申告が必要です。
- マイホーム売却にかかる3,000万円の特別控除特例
- マイホーム売却時の長期譲渡所得6,000万円までの軽減税率
- マイホーム買換えの譲渡損失の繰越控除(損益通算)
税務署に申告するのは、譲渡所得金額がいくらだったのかという数字についてです。
譲渡価額
購入価格+固定資産税精算金
※所有権移転日(残金決済日)に売り主と買い主で固定資産税を精算し戻ってきた分があれば。
取得費(もしくは概算取得費)
売却価格(建物の場合は減価償却費を差し引いた金額)
取得時の売買契約書や領収書を無くして購入金額不明の場合は、売却金額の5%とする
取得にかかる仲介手数料などの経費を引いたもの
減価償却費
経過年数は購入からの所有期間で、6ヶ月単位で判定(6ヶ月以上を1年とする、6ヶ月未満は切り捨て)
係数は建物の構造で決められている
減価償却費相当額=建物購入価額×0.9×償却率×経過年数
構造別償却率と耐用年数
| 建物の構造 | 耐用年数 | 償却率 |
|---|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 |
| れんが造、石造又はブロック造 | 57年 | 0.018 |
| 金属造 骨格材の肉厚4mm超 | 51年 | 0.020 |
| 金属造 骨格材の肉厚3mm超4mm以下 | 40年 | 0.025 |
| 金属造 骨格材の肉厚3mm以下 | 28年 | 0.036 |
| 木造又は合成樹脂造 | 33年 | 0.031 |
| 木骨モルタル造 | 30年 | 0.034 |
引用:国税庁
確定申告に使う書類(A・B・Cは税務署で手に入ります)
(A)確定申告書B
不動産所得もしくは事業所得がある人用の書式です。
(B)分離課税用の申告書
不動産売却益は給与所得とは分離して課税されます。
(C)譲渡所得内訳書
売却で得られた利益を土地・建物に分けて記載します。
(D)不動産売買契約書
マイホーム売却の売買契約書(コピー)です。
(E)登記事項証明書
いわゆる土地と建物の登記簿謄本です。法務局にて有料で入手します。
(F)領収書
マイホーム購入費用・固定資産税精算書・仲介手数料・その他の経費のものです。
ネットの情報や不動産仲介担当者からの情報を完全に鵜呑みにせず、必ず税務署や税理士に相談して、書類や記載内容を間違わないように気をつけて手続きしましょう。
家を売った時の税金をあらかじめ理解しておこう。
マイホームを売却する際にはいろいろな税金やその他の費用がかかります。
いくつかの節税のための特例がありますが、併用できるものとできないものがあります。
またそれらの特例を使うためには必要書類を揃えて確定申告をしなければなりません。
手際よく間違いなく行うためにも、事前によく確認しながら慎重に進めましょう。
不動産の売却先でお悩みの方は、一括査定のおうちクラベルをご利用ください。ヤフーとSREホールディングスが共同運営しているサービスなので信頼できるサイトといえます。特に、「仲介手数料が0円」というのもポイントです。
Q.マイホームを売却する時にどんな税金がかかりますか?
A.印紙税・消費税・登録免許税・所得税・住民税・復興特別税などです。
税金以外にもさまざまな費用がかかります。
Q.節税の特例は自動的に適用されますか?
A.自分で手続きが必要です。必要書類を揃えて税務署へ確定申告をしましょう。
適用する特例によっては数年間にわたる確定申告が必要な場合もあります。