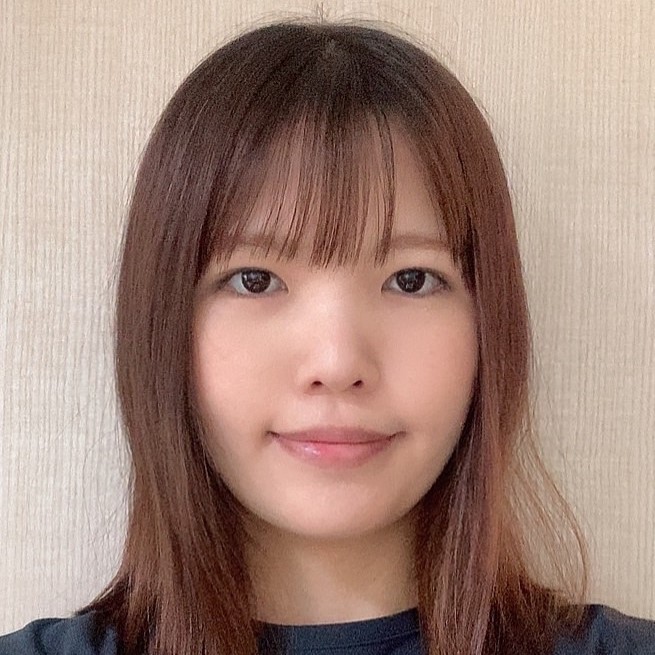家を売る際は、何から始めればよいのでしょうか?
家を売りたいと考えても、何から始めればよいのかわからない場合も少なくないでしょう。
今回は、家を売るための手順や流れ、注意点、かかる税金などをまとめて解説します。
この記事を参考に、ぜひ後悔のない家の売却を目指してください。
家を売る基本的な手順・流れ
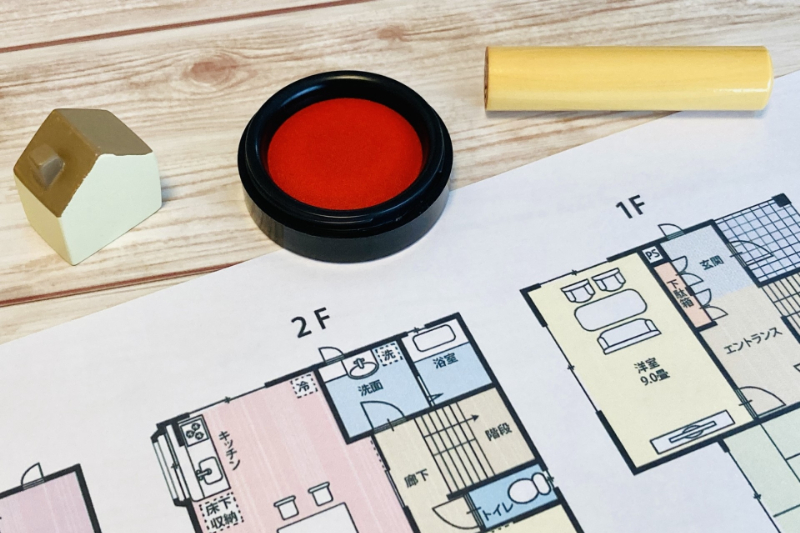
家を売る際は、どのような手順で売却を進めるとよいのでしょうか?
はじめに、家を売る基本的な手順と流れを解説します。
- 不動産会社に査定の依頼をする
- 家にローンがある場合はあらかじめ金融機関に相談する
- 家の売却を依頼する不動産を選定する
- 家の売り方を相談する
- 不動産会社と媒介契約を締結する
- 家を売りに出す
- 内見に対応する
- 売買契約を締結する
- 決済をして家を引き渡す
- 確定申告をする
不動産会社に査定の依頼をする
家を売りたい場合は、不動産会社へ査定の依頼をします。
査定とは、不動産会社にその家や土地の売却想定額を算定してもらう手続きです。
査定は1社のみではなく、複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。
なぜなら、査定は不動産会社のノウハウを基に算定されたものであり、不動産会社によって査定額が異なることも珍しくないためです。
しかし、自分で複数の不動産会社を回って査定の依頼をしていては、膨大な時間や手間を要します。
また、自分から不動産会社にコンタクトをとった場合は、その不動産会社へそのまま売却の依頼をする流れとなりやすく、十分に比較できないまま最初に連絡した不動産会社に依頼することとなる場合も少なくありません。
そこでおすすめなのが、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」のご利用です。
おうちクラベルは、1度の入力で複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。
おうちクラベルを利用すれば、自分で1社1社不動産会社を回る必要はありません。
家にローンがある場合はあらかじめ金融機関に相談する
売却を検討している家に、ローンが残っている場合もあるでしょう。
この場合は、査定結果が出た時点で金融機関へ相談することをおすすめします。
その結果、売却額がローン残債を上回る「アンダーローン」となることが見込まれる場合は、売却対価でローン残債を完済できるため問題ありません。
一方、売却額がローン残債を下回る「オーバーローン」となる場合は、次の対策などを検討する必要が生じます。
- 自己資金などでローン残債を完済する
- ローン残債と住み替え先となる家の購入費用を1本のローンにまとめる「住み替えローン」を活用する
いずれも難しい場合は、家に付いている抵当権(担保)の抹消ができず、事実上家の売却ができないかもしれません。
早期に金融機関へ相談しておくことで、売却の見通しを立てることが可能となります。
家の売却を依頼する不動産を選定する
査定結果が出揃ったら、家の売却を依頼する不動産会社を選定します。
不動産会社は査定額の高さのみで決めるのではなく、査定額への説明や担当者の誠実さなどを踏まえて選定するとよいでしょう。
なぜなら、査定額はあくまでもその不動産会社が考える売却想定額でしかなく、その価格で売れる保証はないためです。
家の売り方を相談する
家の売却を依頼する不動産会社を選定したら、その不動産会社に家の売り方を相談しましょう。
家の築年数が浅い場合は、その家と土地をセットで売ることが一般的です。
一方、家が古い場合は、次の売り方などが選択肢となります。
- 家と土地をそのまま売る
- 家をリフォームして家と土地を売る
- 家を解体して土地のみを売る
いずれの方法が適しているかは、家の状態やその地域のニーズによって異なります。
自分1人で考えるのではなく、不動産会社からのアドバイスを踏まえて検討するとよいでしょう。
なお、売却を急がない場合は「1」の方法で売り出し、一定期間買主がつかない場合に「2」や「3」の方法を検討することも1つの手です。
不動産会社と媒介契約を締結する
次に、不動産会社との間で媒介契約を締結します。
媒介契約は次の3種類があります。
状況や希望に合った契約を選択してください。
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 他の不動産会社へ重ねての依頼 | 不可 | 不可 | 可 |
| 自己発見取引 (自分で買主を見つけての売買) | 不可 | 可 | 可 |
| 指定流通機構への登録 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | 義務なし |
| 報告頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 指定なし |
家を売りに出す
不動産会社と媒介契約を締結したら、家を売りに出します。
家を売り出す際は、売主の希望売却価格である売出価格を決定します。
売出価格は、査定額をベースとして売主の希望を加味して決めることが多いでしょう。
内見に対応する
家を売りに出すと、購入希望者から物件についての問い合わせが入ります。
原則として、問い合わせには不動産会社が対応するため、自分で直接買主からの問い合わせなどに対応する必要はありません。
家の買主は、購入を決める前に内見を希望することが一般的です。
内見時は、可能な限り売主本人も立ち会うことをおすすめします。
なぜなら、売主が立ち会って丁寧に対応することで、買主が安心して購入を決めやすくなるためです。
また、居住中の物件でも、売買契約を成立させるためは内見を積極的に受け入れた方がよいでしょう。
売買契約を締結する
買主が購入を決めたら、家や土地の売買契約を締結します。
売買契約書は、一般的に不動産会社が作成してくれます。
売買契約の締結時は、買主から売主へ手付金の交付がされることが一般的です。
手付金の額に明確な決まりはないものの、売却代金の5%から10%程度とされることが多いです。
決済をして家を引き渡す
あらかじめ取り決めた決済日に、次のことを行います。
決済は、買主がローンを組む金融機関の応接室などで行われることが多いでしょう。
決済は、次のことが同時に行われることが一般的です。
- 売主から買主へ家や土地の名義を変えるために必要な書類への署名押印
- 買主の住宅ローンの実行
- 買主から売主への売買代金全額(手付金を除く)の支払い
また、売却する家にローンが残っている場合は、次のことも同時に行われます。
- 売主側のローン契約先の金融機関から、抵当権抹消に必要な書類の交付
- 売主側のローン残債の完済
決済後は、この場に立ち会った司法書士が登記を申請して、家や土地の名義が買主へと変わります。
確定申告をする
家や土地を売って利益(譲渡益)が出る場合は、譲渡所得税の課税対象となります。
そのため、売却の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。
譲渡所得税の対象となる場合は、忘れずに確定申告を行ってください。
家を売る際の注意点:事前準備

家を売る際は、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
事前準備における主な注意点は次のとおりです。
- 査定は複数の不動産会社に依頼する
- その家の売却に強い不動産会社に依頼する
- 自己判断で解体やリノベーションをしない
- オーバーローンとならないことを確認しておく
査定は複数の不動産会社に依頼する
先ほども解説したように、家を売る際の査定は複数の不動産会社に依頼するとよいでしょう。
複数社による査定額を比較することで、その家や土地の売却適正額が把握しやすくなるためです。
複数社への査定の依頼は、ぜひ「おうちクラベル」をご利用ください。
その家の売却に強い不動産会社に依頼する
家や土地を売る際は、その家や土地の売却に強い不動産会社に依頼することが成功のカギとなります。
なぜなら、その家や土地の売却についてノウハウのある不動産会社は、メリットを十分に訴求してよりよい条件で売ってくれる可能性が高いためです。
しかし、どの不動産会社がその家や土地の売却に強いのかわからない場合も多いでしょう。
その際は、不動産一括査定ができる「おうちクラベル」のご利用がおすすめです。
複数社に査定の依頼をすることで、その家や土地の売却に強い不動産会社を見つけやすくなるでしょう。
自己判断で解体やリノベーションをしない
家を売るにあたって、独断で解体やリノベーションをすることはおすすめできません。
なぜなら、解体をしなくても売れる可能性があるほか、自由にリノベーションをしたいという買主のニーズが見込める可能性があるためです。
そのため、解体やリノベーションは、あらかじめ不動産会社へ相談したうえで決めるようにしてください。
オーバーローンとならないことを確認しておく
先ほども解説したように、オーバーローンとなる場合は希望どおりの売却が実現できない可能性があります。
そのため、家を売る際はまずオーバーローンとならないことを確認しておくことが必要です。
オーバーローンとなりそうな場合は、特に早い段階から金融機関に相談してください。
家を売る際の注意点:売却活動中

続いて、売却活動中に主に注意すべきことは次のとおりです。
- 売出価格を高めに設定する
- 内見に丁寧に対応する
- 内見時は清掃や整理整頓を心がける
- 故障や不具合を隠さない
売出価格を高めに設定する
家をよりよい条件で売りたい場合は、売出価格を少し高めに設定するとよいでしょう。
家や土地に相場はあるものの、買主が見つかればいくらで売っても構わないためです。
ただし、相場よりあまりにも高くしすぎると、買主が見つからないかもしれません。
売出価格は、その家の売却に強い不動産会社に相談して決めることをおすすめします。
その家の売却に強い不動産会社をお探しの際は、ぜひ「おうちクラベル」をご利用ください。
内見に丁寧に対応する
家を解体せずに売る場合は、内見への対応が必要となります。
内見は売主自身も立ち会って丁寧に対応することで、その家や土地がよりよい条件で売れる可能性が高くなるでしょう。
内見時は清掃や整理整頓を心がける
内見の受け入れ前は、清掃や整理整頓をしておくようにしてください。
引き渡しの後に売主側の私物が撤去されてハウスクリーニングがされることがわかっていても、汚れて散らかった状態では購入意欲が湧きにくいためです。
故障や不具合を隠さない
中古住宅では、設備などに何らかの不具合があることが多いです。
このような不具合は隠さずに、買主へ正直に申告してください。
不具合を隠したまま家を売ると、引き渡し後に「契約不適合責任」を追及されてトラブルとなる可能性があるためです。
契約不適合責任とは、契約と合致しない物件を引き渡したことについて売主が問われる責任のことであり、補修の請求や代金減額請求、損害賠償請求などがなされる可能性があります。
なお、売主が知らない不具合については、契約によって契約不適合責任を制限したり免除したりすることも少なくありません。
仲介の依頼をしている不動産会社にこの点も相談しておくとよいでしょう。
家を売る際の注意点:売却後編

続いて、売買契約成立後の主な注意点は次のとおりです。
- 引き渡し前に速やかに私物を撤去する
- 確定申告を忘れない
引き渡し前に速やかに私物を撤去する
売却する家に売主の私物がある場合は、遅くとも引き渡しの時までにすべて撤去してください。
荷物の量が多い場合は、搬出に相当な時間と手間がかかる可能性があります。
そのため、余裕をもったスケジュールを設定しましょう。
確定申告を忘れない
家や土地を売って利益が生じる場合は、これに譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の対象となる場合は、家を売った年の翌年2月16日から3月15日までの間に、忘れずに確定申告を行ってください。
確定申告が必要であるかどうかわからない場合は、あらかじめ税理士などの専門家へ相談しておくとよいでしょう。
家を売る際のその他の注意点・ポイント

家をよりよい条件で売るには、次の点にも注意が必要です。
- 家の売却を急がない
- 家のニーズが高まる時期を知っておく
- 状況によっては不動産買取を検討する
家の売却を急がない
家を売る際は、売却を急がないようにしてください。
家の売却を急ぐと、買主から足元を見られて安い価格で買い叩かれてしまうかもしれないためです。
家の売却は、時間に余裕を持って行うことをおすすめします。
家のニーズが高まる時期を知っておく
家の売買は、毎年2月から3月頃に活発となる傾向にあります。
なぜなら、4月からの転勤や子どもの入学などに向けて引っ越し先となる家を購入する人が増えるためです。
この時期に家を売りに出すことで、よりよい条件で売却できる可能性があります。
状況によっては不動産買取を検討する
不動産買取とは、不動産会社に直接家や土地を買い取ってもらう取引形態のことです。
不動産買取の場合の売買価格は、市場での売却の6割から8割程度となることが一般的です。
一方で、売買契約の成立までがスピーディーであったり、市場で売りづらい家や土地であっても買い取ってもらえる可能性があったりするなど、メリットも少なくありません。
そのため、家や土地の売却を急ぐ場合や、市場での買主がなかなか見つからない場合などは、不動産買取によって売ることも検討するとよいでしょう。
家を売る際にかかる費用・税金

家を売る際は、さまざまな費用や税金がかかります。
ここでは、主にかかる費用と税金について解説します。
- 仲介手数料
- 家の解体費用
- ハウスクリーニング費用
- 測量費用
- 印紙税
- 抵当権の抹消費用
- 譲渡所得税
仲介手数料
不動産会社に家を売ることを依頼して売買契約が成立した際は、不動産会社に仲介手数料の支払いが発生します。
仲介手数料の額は不動産会社が自由に決められるものではなく、次のとおり法令で上限額が定められています。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 売却価格の5%+消費税 |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 売却価格の4%+消費税 |
| 400万円を超える部分 | 売却価格の3%+消費税 |
なお、売却価格が400万円超である場合は、次の算式にまとめて計算することも可能です(計算結果は同じになります)。
- 仲介手数料の上限額=売却価格×3%+6万円+消費税
家の解体費用
家を売る際は、家と土地をまとめて売る場合のほか、古い家を解体して土地のみを売却する場合もあります。
この場合、家の解体費用が必要です。
解体費用は依頼先の建設会社によって異なるものの、1坪あたりの家の解体費用の目安は次のとおりです。
| 種別 | 解体費用の目安 |
|---|---|
| 木造 | 3万~5万円 |
| 鉄骨造 | 4万~6万円 |
| 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 6万~8万円 |
ただし、立地や周辺の道路環境、隣家との密接度合いなどによって異なるうえ、高額となることが少なくないため、あらかじめ見積もりをとるとよいでしょう。
ハウスクリーニング費用
家を解体せずに売る場合は、引き渡しの前にハウスクリーニングを入れることが多いです。
ハウスクリーニング費用は依頼先の清掃会社によって異なるものの、おおむね6万円から15万円程度となることが多いでしょう。
ただし、広さや間取り、汚れ具合などによって費用は異なります。
あらかじめ依頼を検討している清掃会社に料金を問い合わせ、必要に応じて見積もりをとるとよいでしょう。
測量費用
測量とは、隣地との境界を明確にしたり、土地の面積を正しく算定したりする手続きです。
家の敷地である土地を売るにあたって、測量が必須というわけではありません。
しかし、実際は後のトラブルを防ぐため、境界が明確となっている場合を除いて測量を行うことも少なくありません。
測量費用は、隣地の種類によっておおむね次の金額が目安となります。
| 隣地の種類 | 測量費用の目安 |
|---|---|
| 隣接地が民有地 | 35万円~45万円 |
| 隣接地が官有地(国有地) | 60万円~80万円 |
ただし、土地の形状や広さなどによって大きく異なる可能性があるため、あらかじめ見積もりをとることをおすすめします。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書などの文書に対して課される税金です。
家や土地の売買契約書も印紙税の課税対象であり、税額はそれぞれ次のとおりです。
なお、2024年3月31日までに作成をした契約書では、軽減税率が適用されています。
| 契約金額 | 印紙税額 (2024年年3月31日までの軽減税率) |
|---|---|
| 50万円以下 | 200円 |
| 100万円以下 | 500円 |
| 500万円以下 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 160,000円 |
| 50円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
家や土地の売買契約書は、2通作成したうえで売主と買主がそれぞれ1通保管することが一般的です。
印紙税も、売主と買主それぞれが保管する契約書に貼付する分を負担することが多いでしょう。
抵当権の抹消費用
抵当権が付いている家や土地を売る際は、遅くとも引き渡しの時点までに抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権を抹消する際は、次の費用がかかります。
| 費用 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 抵当権を抹消する不動産の数×1,000円 |
| 司法書士報酬 | 1万円~2万円程度 |
なお、抵当権を抹消するには、原則としてローンを完済しなければなりません。
ローンの繰り上げ返済にあたっては、金融機関によって1万円から3万円程度の手数料がかかる場合があります。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、家や土地を売って得た「儲け」に対してかかる税金です。
譲渡所得税は、次の式で計算します。
- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率
計算要素の概要は、それぞれ次のとおりです。
| 計算要素 | 概要 |
|---|---|
| 収入金額 | 家や土地の売却で買主から得る対価 |
| 取得費 | その家や土地の取得に要した購入代金、建築代金、仲介手数料、不動産取得税など(不明な場合は収入金額×5%で計算する。また、家は所有期間分の減価償却費相当額の控除が必要) |
| 譲渡費用 | その家や土地を売却するために直接かかった仲介手数料や印紙税、土地を売るために支払った建物の解体費用など |
| 特別控除 | 後ほど解説する「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」や「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」など |
| 税率 | 売却した家の所有期間に応じて15%(長期)または30%(短期)。なお、別途住民税と復興特別所得税が必要 |
譲渡所得税は納付書などが送付されるのではなく、原則として自分で計算をして申告しなければなりません。
譲渡所得税の計算は注意点が多いため、あらかじめ税理士や管轄の税務署などへ相談しておくことをおすすめします。
参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)
家を売る際にかかる税金が安くなる譲渡所得税の主な特例

家を売る際は、譲渡所得税の特例が使える可能性があります。
特例の適用を受けることで、譲渡所得税が安くなる可能性があるほか、結果的に譲渡所得税がゼロとなるケースも少なくありません。
そのため、家を売る際はあらかじめ税理士などの専門家へ相談のうえ、特例適用の可否を確認したり譲渡所得税の試算をしたりしてもらっておくとよいでしょう。
なお、特例の適用を受けた結果譲渡所得税額がゼロとなる場合であっても、特例の適用を受けるには確定申告が必要です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは、自宅であった家や土地を売却した際に、一定の要件を満たすことで最大3,000万円の控除が受けられる特例です。
自宅として使っている家を売る場合は、この特例の適用を受けられる可能性があるでしょう。
なお、家を壊して土地のみを売った場合でも、この特例の適用を受ける余地はありますが、家を壊してから1年以内かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに敷地を売ることや、家の解体後に土地を貸し駐車場などとして使っていないなどの要件を満たさなければなりません。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除の特例
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除の特例」とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)が生前住んでいた空き家やその敷地を売却した場合に、一定の要件を満たすことで最大3,000万円の控除が受けられる特例です。
被相続人が亡くなったことで空き家となった一軒家を売る際は、この特例の適用を受けられる可能性があるでしょう。
ただし、この特例はマンションなど区分所有登記がされた建物は活用できないほか、昭和56年5月31日以前に建築された建物であることや相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなど、建物に関する要件もあることに注意が必要です。
参照元:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは、相続によって取得した家や土地を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合、その家や土地にかかった相続税を譲渡所得税の計算上「取得費」に加算することができる特例です。
たとえば、家の売主がその相続で支払った相続税が600万円であり、その者が受け取った相続税の課税対象となった財産総額が3,000万円、売却した家や土地の相続税計算上の評価額が1,000万円である場合、次の額を取得費に加算することができます。
- 取得費に加算できる額=600万円×1,000万円÷3,000万円=200万円
参照元:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(国税庁)
不動産会社の選び方のポイント

家を売る際は、不動産会社に仲介の依頼をすることが一般的です。
では、家の売却を依頼する不動産会社はどのように選定すればよいのでしょうか?
不動産会社を選ぶ主なポイントは次のとおりです。
- 査定額への説明が明確な不動産会社を選ぶ
- 宅建免許の更新回数を確認する
- 仲介手数料の安さのみでは選ばない
査定額への説明が明確な不動産会社を選ぶ
1つ目は、査定額の説明が明確である不動産会社を選ぶことです。
査定額は不動産会社による家の売却予想額であり、その価格で家が売れるという保証ではありません。
しかし、その家の売却を依頼する不動産会社を選ぶ際は、査定額を参考に依頼先の不動産会社を選ぶこともあるでしょう。
査定額が高いほど、家を高値で売ってくれるとの期待がされやすいためです。
そのため、中には売却の依頼を受けたいがために、根拠のない高めの査定額を提示する不動産会社もあります。
そのような不動産会社に依頼をすると、結果的に査定額から大きく値を下げないと家が売れない可能性が高いと考えられます。
そのような事態を避けるため、家の売却を依頼する不動産会社を選ぶ際は、査定額の根拠について説明を求めることをおすすめします。
特に、他の不動産会社よりもとびぬけて高い査定額を提示された場合は、他社より高い根拠についての説明を受けるべきでしょう。
説明を断られた場合や、説明があいまいであったり難解な用語を用いて説明をされたりして納得感が得られない場合は、その不動産会社への依頼はおすすめできません。
信頼できる不動産会社をお探しの際は、「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。
おうちクラベルから査定の依頼をすることができる不動産会社は実績豊富な優良企業ばかりであり、安心してご利用いただくことが可能です。
宅建免許の更新回数を確認する
家の売買の仲介をするには、宅建免許を所有していなければなりません。
宅建免許は5年ごとの更新制であり、免許番号は「国土交通大臣免許(1)〇〇〇〇〇号」や「東京都知事(2)第〇〇〇〇〇号」などのように表記されます。
このカッコ内の数字は、宅建免許の更新回数を示しています。
1回目の更新を迎えていない不動産会社ではカッコ内の番号が「1」であり、すでに1回免許更新をした不動産会社はカッコ内の数字が「2」、5回更新をした不動産会社は「6」となります。
つまり、このカッコ内の数字が大きければ大きいほど宅建免許の更新回数が多く、長く事業を営んでいることが読み取れます。
業歴が長いからといって、必ずしも信頼できる不動産会社であると断言できるわけではありません。
しかし、少なくともその期間中は免許の取り消しを受けるほどの大きな問題を起こさず、事業を継続できるだけの収益を得ながら事業を営んできたことがわかります。
そのため、免許番号のうちカッコ内の数字も不動産会社を選定する際の1つの判断材料となるでしょう。
仲介手数料の安さのみでは選ばない
不動産会社に家の売却を依頼する場合は、売買契約が成立した時点で仲介手数料の支払いが発生します。
仲介手数料の上限額は、先ほど解説をしたとおりです。
しかし、中には売主側の仲介手数料を格安とする不動産会社もあります。
売れた家の価格が高い場合は仲介手数料も高額となるため、仲介手数料が格安であることには魅力を感じる場合もあるでしょう。
しかし、仲介手数料の安さのみで家の売却を依頼する不動産会社を選ぶことはおすすめできません。
なぜなら、仲介手数料が安いと、売却にあたって十分なフォローが受けられない可能性があるためです。
また、売主側の仲介手数料が格安である場合、両手仲介を前提とした囲い込みがなされる可能性が高いことも考えられます。
両手仲介とは、1社の不動産会社が売主と買主の双方から不動産売買の依頼を受けることです。
この場合、不動産会社は売主と買主の双方からそれぞれ仲介手数料を受け取ることができます。
この両手仲介自体に問題があるわけではありません。
なぜなら、不動産会社が独自のネットワークや販売力を駆使してスムーズに買主を見つけてくれれば、売主にとってもメリットが大きいためです。
また、両手仲介であるからといって、売主の支払う仲介手数料が増えるわけでもありません。
しかし、無理矢理両手仲介に持ち込むために囲い込みが発生すると、売主にはデメリットが大きくなります。
囲い込みとは、たとえば他の不動産会社経由で家の購入打診があった際に、「その家はもう売れた」などと嘘をついて取引を断ることなどです。
そのため、仲介手数料の安さのみで不動産会社を選定することは避けた方がよいでしょう。
信頼できる不動産会社をお探しの際は、ぜひ「おうちクラベル」をご利用ください。
まとめ
家を売る際は、はじめに不動産会社に査定の依頼を行います。
査定は1社のみではなく、複数の不動産会社に依頼しましょう。
査定額や査定額への説明などを比較することで、その家の売却に強い信頼できる不動産会社を見つけやすくなるためです。
しかし、自分で複数の不動産会社に査定の依頼をしようとすると、多大な手間と時間を要します。
そこでおすすめなのが、「おうちクラベル」のご利用です。
おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。
査定依頼先となる不動産会社は実績豊富な優良企業ばかりであり、安心してご利用いただくことができます。