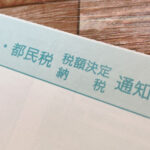農地を売りたいと考えても、どのように進めるべきかわからない場合も多いでしょう。
農地を売却する方法には、「農地のまま売却する方法」と「宅地に転用して売る方法」の2つがあります。
では、それぞれどのような流れで進めるとよいのでしょうか?
今回は、農地を売るための流れや必要な手続きなどについて詳しく解説します。
農地の売却が難しい理由

農地は耕作の目的に供される土地を指し、畑や田などが該当します。
一般的に、農地の売却は難しいといわれることが少なくありません。
なぜなら、農地以外の土地とは異なり、「農地法」によって売却や転用(農地以外のものに変えること)が厳しく規制されているためです。
この農地法の規制により、農地を売るには農業委員会から許可を受けなければなりません。
農地が日本の食糧を生み出す貴重な役割を持つことから、むやみに減らさないようにすべきとの考えによるものです。
また、許可を受けるには要件があり、農地のままで売るには原則として購入者が農業従事者であることなどが求められます。
農地を売却する際は、許可が下りる見込みがあるかどうかを調べたうえで、慎重に手続きを進める必要があります。
農地を売る2つの方法

農地を売却する方法には、次の2つがあります。
いずれの方法で売るのかによって、必要な手続きや流れが大きく異なります。
- 農地のまま売却する
- 宅地などに変えて売却する
農地のまま売却する
1つ目は、農地のままで売却する方法です。
農地のままで売るには、買い手は原則として農業従事者でなければなりません。
農地法上の手続きは農地法の条文番号で呼ばれることが多く、この場合は「3条」の許可が必要となります。
宅地などに変えて売却する
2つ目は、宅地などに転用して売却する方法です。
転用して売却する場合、買い手に制限はありません。
こちらは、農地法「5条」の許可の対象となります。
ただし、農地転用の許可は厳しく、所定の用紙を出したからといって簡単に許可が出るような性質のものではありません。
特に周囲に農地が広がっている地域では、転用の許可が下りない可能性が高くなります。
そのため、後ほどの流れの中で解説しますが、許可の見込みを調べたうえで売却を進める必要があります。
農地のまま売却する方法・流れ

農地のまま売却する際の基本的な流れと方法は、次のとおりです。
- 農地の買い手を探す
- 売買契約を締結する
- 農業委員会へ許可申請をする
- 所有権移転の仮登記をする
- 許可が下りたら所有権移転登記をする
農地の買い手を探す
農地のまま売却する場合、買い手が購入後に農業に従事すると認められなければなりません。
農地法3条の許可では、買い手についても審査がされます。
審査の結果、農地の取得後に買い手がその農地全体を効率的に利用して耕作を行うことが認められない場合、許可を受けることができず農地を売却できません。
そのため、農地のまま売却する際は、付近の農家などへ打診して自分で買い主を探すか、地域の農業委員会やJA(農業協同組合)などからあっせんを受けて買い手を探すことが一般的です。
売買契約を締結する
購入希望者が見つかったら、買い手との間で売買契約を締結します。
ただし、この段階ではまだ農業委員会から売却の許可が得られると決まったわけではなく、不許可になると農地の名義変更ができません。
そのため、「売買契約書には不許可になった場合には自動的にこの契約が解約され、農地を引き渡せなかったことについて双方ともに責任を負わない」旨の規定を入れる必要があります。
農業委員会へ許可申請をする
売買契約を締結したら、地域の農業委員会へ3条許可の申請を行います。
許可申請に必要な書類は地域によって異なる可能性があるため、その地域の農業委員会に確認したうえで必要書類を集めてください。
また、地域によっては許可申請を毎日受け付けておらず申請できる日が限定されていることもあるため、スケジュールも確認しておくことをおすすめします。
許可申請の手続きは自分で行うこともできますが、農地転用を多く取り扱っている行政書士へ依頼するとスムーズです。
所有権移転の仮登記をする
許可申請から許可が下りるまでの期間は地域によって異なるものの、30日程度とされていることが多いようです。
そのため、必要に応じて法務局で所有権移転の仮登記を行います。
仮登記とは、将来的な登記を保全するために行う仮の登記のことです。
登記のルール上、登記が二重でされた場合は、先に登記した方が優先されます。
たとえば、X土地の売主であるA氏がB氏と売買契約を締結した後、別のC氏とも売買契約を締結した場合、B氏とC氏のいずれがA土地を取得するのかは、B氏とC氏のどちらの登記が早かったかによるということです。
C氏が先に登記を申請すると、B氏はX土地の所有権を得ることができません(あとは、B氏からA氏への損害賠償請求の問題となります)。
そのため、土地の買主はその土地を他者に「横取り」されないよう、できるだけ早く登記申請をしたいと考えます。
しかし、農地の売却には農業委員会の許可が必要であり、許可を受けるまで正式な名義変更登記をすることができません。
そこで仮登記をしておくことで登記の順位を確保することが可能となり、仮登記の後で登記をした第三者に対応することが可能となります。
そのため、農地の売買実務では仮登記がよく活用されています。
許可が下りたら所有権移転登記をする
農業委員会から許可が下りたら、農地を正式に名義変更することが可能となります。
この正式な名義変更登記を、「仮登記」に対して「本登記」といいます。
宅地などに変えて売却する方法・流れ
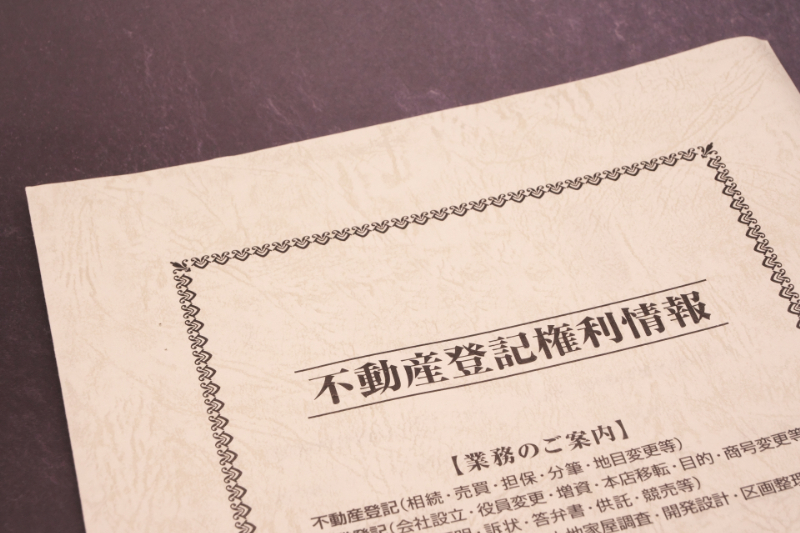
農地を宅地などへ転用して売却する方法と流れは次のとおりです。
- 転用の見込みがあるかどうかを調べる
- 不動産会社に査定の依頼をする
- 売却を依頼する不動産会社を選定する
- 不動産会社と媒介契約を締結する
- 農地を売りに出す
- 売買契約を締結する
- 農業委員会に許可申請をする
- 所有権移転の仮登記をする
- 許可が下りたら所有権移転登記をする
転用の見込みがあるかどうかを調べる
はじめに、その農地の転用見込みを調査します。
農地がある場所によっては、転用が許可される見込みがほとんどない可能性があるためです。
その位置や自然環境によって、農地は次の5つに区分されており、それぞれで許可方針が異なります。
表中の上にあればあるほど農業に適した地域(農地が広がっている地域のイメージ)であり転用のハードルが高く、下にいくほど市街地(街中や住宅地にポツンと農地があるようなイメージ)となり転用のハードルも低くなります。
| 農地区分 | 概要 | 許可見込み |
|---|---|---|
| 農振農用地区域内農地 | 市町村が「農振農用地区域」に指定した区域内の農地 | 原則不許可。転用する場合には先に農振農用地区域から外す手続きが必要でありハードルが高い |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可。特例に許可がされる可能性はあるがハードルが高い |
| 第1種農地 | 良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可。特例に許可がされる可能性はあるがややハードルが高い |
| 第2種農地 | 「市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域などにある農地で、他のいずれにも該当しない農地 | 他に代替地がない場合などには許可 |
| 第3種農地 | 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則許可 |
農業委員会に相談して売却したい農地の区分を知り、許可見込みの有無を確認します。
自分で調べることが難しい場合は、農地転用を多く取り扱っている行政書士へ依頼するとスムーズです。
不動産会社に査定の依頼をする
転用の見込みがあることがわかったら、不動産会社に査定の依頼をします。
査定とは、不動産会社に農地の売却見込み額を算定してもらう手続きです。
査定は1社のみではなく、複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。
なぜなら、査定額は不動産会社によって異なることが一般的であり、1社のみに依頼するだけだとその査定額が適正であるかどうか判断することが難しいためです。
一方、複数の不動産会社へ査定の依頼をするとその農地の売却適正額が把握しやすくなるほか、その農地をよりよい条件で売却してくれる不動産会社を見つけやすくなります。
しかし、自分で1社1社不動産会社を回って査定の依頼をするには、膨大な手間と時間を要します。
そこでおすすめしたいのが「おうちクラベル」のご利用です。
おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。
査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができるため、自分で複数の不動産会社を回る必要はありません。
売却を依頼する不動産会社を選定する
不動産会社による査定が出揃ったら、農地の売却を依頼する不動産会社を選定します。
不動産会社は査定額の高さのみではなく、査定額の根拠の明確さや担当者の誠実さなどを総合的に判断して決めるようにしてください。
なぜなら、査定額はあくまでもその不動産会社が考える売却見込額でしかなく、必ずしもその価格で農地が売却できる保証ではないためです。
不動産会社と媒介契約を締結する
農地の売却を依頼する不動産会社を選定したら媒介契約を締結します。
媒介契約には次の3種類があります。
状況や希望に合った契約を選定してください。
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 他の不動産会社へ重ねての依頼 | 不可 | 不可 | 可 |
| 自己発見取引 (自分で買主を見つけて売却すること) | 不可 | 可 | 可 |
| 指定流通機構(レインズ)への登録義務 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | 義務なし |
| 報告頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 指定なし |
媒介契約は、3つのうちどれを選択しても構いません。
ただし、農地の売却では、不動産会社からさまざまな助言を受けたり行政書士の紹介を受けたりすることが多いでしょう。
そのため、不動産会社から十分なフォローを受けたい場合は「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」を選ぶことをおすすめします。
農地を売りに出す
不動産会社と媒介契約を締結したら、農地を売りに出します。
農地を売りに出す際は、売り手の希望売却価格である「売出価格」を決めます。
一般的に、査定額をベースとして設定します。
売買契約を締結する
買い手が見つかり条件交渉がまとまったら、売買契約を締結します。
ただし、農地のまま売却する場合と同じく、この段階ではまだ農地法上の許可が下りると決まっているわけではありません。
そのため、売買契約書に「売買契約書には不許可になった場合には自動的にこの契約が解約され、農地を引き渡せなかったことについて双方ともに責任を負わない」旨の規定を入れる必要があります。
農業委員会に許可申請をする
売買契約を締結したら、農業委員会へ農地法5条許可の申請を行います。
許可申請に必要な書類は地域によって異なる可能性があるため、その地域の農業委員会に確認したうえで必要書類を集めてください。
また、3条許可と同じく許可申請を毎日受け付けておらず、申請できる日が限定されていることがあるため、スケジュールも確認しておくことをおすすめします。
許可申請の手続きは、行政書士へ依頼するとスムーズです。
所有権移転の仮登記をする
許可申請をしたら、所有権移転の仮登記を行います。
仮登記については、先ほど農地のまま売却する場合の流れで解説したとおりです。
許可が下りたら所有権移転登記をする
農地法の許可が下りたら、正式に所有権移転の本登記をします。
これで、土地の名義が買主へと変わります。
売買代金の授受は、この本登記と同時に行うことが一般的です。
なお、農地転用の許可が下りると農地を宅地へ造成することとなりますが、これは引き渡し後に買主が行うため、原則として売主が行う必要はありません。
農地の売却にかかる主な費用・税金

農地の売却では、さまざまな費用や税金がかかります。
主にかかる費用や税金は次のとおりです。
- 仲介手数料
- 行政書士報酬
- 印紙税
- 譲渡所得税
仲介手数料
不動産会社の仲介によって農地を売買が成立した場合は、不動産会社の報酬である仲介手数料の支払いが発生します。
仲介手数料の上限額は法令で定められており、それぞれ次のとおりです。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 売却価格の5%+消費税 |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 売却価格の4%+消費税 |
| 400万円を超える部分 | 売却価格の3%+消費税 |
これは「上限額」であるものの、この上限額をそのまま報酬額として定めている不動産会社がほとんどです。
なお、売買価格が400万円超である場合は、次の算式にまとめて計算することができます。
- 仲介手数料の上限額=売却価額×3%+6万円+消費税
行政書士報酬
農地法上の許可申請手続きを行政書士へ依頼する場合、行政書士報酬が発生します。
行政書士報酬は農地の区分などによって異なるものの、おおむね5万円から15万円程度です。
ただし、放縦額や報酬の算定方法は依頼先の事務所によって異なるため、依頼前に報酬額を確認してください。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収証などの書類に課される税金です。
農地など土地の売買契約書も、印紙税の課税対象とされています。
印紙税額は農地の売買価格(契約金額)に応じ、それぞれ次のとおりです。
2024年3月31日までに作成された契約書では、軽減税率が適用されます。
| 契約金額 | 印紙税額 (2024年年3月31日までの軽減税率) |
|---|---|
| 50万円以下 | 200円 |
| 100万円以下 | 500円 |
| 500万円以下 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 160,000円 |
| 50円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
譲渡所得税
譲渡所得税とは、農地などの資産を売却して得た利益に対して課される税金です。
譲渡所得税は国などが計算してくれるわけではなく、自分で計算して確定申告をしなければなりません。
確定申告の期限は、売却の翌年2月16日から3月15日までです。
譲渡所得税の計算には注意点が多く、自分で正しく算定することは容易ではありません。
農地を売却する際は、税理士などの専門家へ相談のうえ、確定申告の要否や譲渡所得税額などについて確認しておくことをおすすめします。
まとめ
農地は農地法の規制対象となっており、売却するには農地法上の許可を受けなければなりません。
中でも農地を転用する許可の難易度は、農地の区分によって異なります。
申請したからといって必ずしも許可が受けられるものではないため、農地を転用して売却したい場合は許可の見込みを確認する必要があります。
転用ができる見込みが立ったら、不動産会社に査定の依頼をして農地の売却を進めましょう。
農地の査定には、ぜひ「おうちクラベル」をご利用ください。
おうちクラベルとは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。
査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、自分で1社1社回る必要はありません。
複数社による査定額を比較することで、その農地の売却適正額を把握できるほか、その農地の売却に強い不動産会社を見つけやすくなります。