モノが要らなくなればごみ箱へ捨てることや欲しがっている人にあげることなど、さまざまな対処法が考えられます。
一方で、手放したいものが土地の場合、簡単に捨てたり人にあげたりすることはできません。さらに要らないからといって土地を放置してしまえば、近隣住民に迷惑がかかったり、損害賠償請求の対象となったりするリスクが生じます。
では不要な土地を手放すにはどうすれば良いのでしょうか?今回は要らない土地を手放す5つの方法についてくわしく解説します。
1.要らない土地や建物を保有し続けるリスク

当面の間は使用する見込みのない不要な土地や建物がある場合、まずはこれをそのまま保有するか、手放すかを検討することになるでしょう。では、要らない土地や建物を保有し続けることには、どのようなリスクがあるのでしょうか?
主なリスクやデメリットは、次のとおりです。
- 管理不全で近隣の迷惑になる
- 損害賠償請求の対象となる
- 固定資産税がかかり続ける
- 手続きの負担が生じる
1-1.管理不全で近隣の迷惑になる
人が利用していない建物は劣化が激しくなる傾向にあるほか、土地にも雑草が生い茂りやすくなります。そのため頻繁に出向いて草刈りや清掃をするなど管理をしなければなりません。
管理を外注することもできますが、その場合には費用がかかります。このような手間や費用を惜しんで放置すれば、家屋が傷んで隙間から忍び込んだ野生動物や虫の住処となったり、伸びた草木が隣地に侵入したりして、近隣住民に迷惑がかかる可能性があるでしょう。
1-2.損害賠償請求の対象となる
土地や家屋が管理不全に陥ると、家屋や塀が倒壊したり、斜面であればがけ崩れが起きたりするなど、危険な状態となります。仮にこれに通行人が巻き込まれるようなことがあれば所有者としての責任が問われ、損害賠償請求がなされる可能性があるでしょう。
1-3.固定資産税がかかり続ける
土地や建物を所有している以上、毎年固定資産税がかかり続けます。「使ってないのだから、払いたくない」といった理屈は通りません。
利用価値の低い土地や建物であれば固定資産税も高額ではない場合が多いかと思いますが、それでも毎年積み重なると、それなりの負担となるでしょう。
1-4.手続きの負担が生じる
土地や建物の情報は、原則として法務局へ登録(登記)されています。これには所有者の住所や氏名も記載されており、住所などに変更が生じれば登記手続きが必要です。
また所有者が亡くなれば、相続人などへと名義を変える相続登記もしなければなりません。
なおこれまでは相続登記などを放置しても罰則はありませんでした。しかし不動産登記法が改正されたことにより、令和6年(2024年)4月1日以降は相続開始後3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料の対象となります。土地や建物を保有している以上、このような手続きの負担が生じ続けることとなるでしょう。
2.手放したい土地を相続でもらった場合に特有の注意点

手放したいと考えている土地が自分で買ったものではなく相続で受け取ったものであるケースも少なくないでしょう。では手放したい土地が相続でもらったものであればどのような点に注意すれば良いのでしょうか?
主な注意点は次のとおりです。
- 先に相続登記を済ませる必要がある
- 一定期間内に売却すると譲渡所得税の特例が受けられる
- 小規模宅地等の特例を利用した土地の場合には税理士に相談する
- 慌てて売ると安く買われてしまうリスクがある
2-1.先に相続登記を済ませる必要がある
原則として、故人名義のままとなっている土地を売却や贈与、寄付などで手放すことはできません。そのため土地が亡くなった人(「被相続人」といいます)の名義である場合にはまず相続登記をすることが必要です。
ただし後ほど解説する「相続土地国庫帰属制度」を利用する際には、例外的に相続登記が不要とされています。また「相続放棄」は他の手続きとは性質が異なりそもそも相続を受けていないため相続登記はできませんし、仮に相続登記をしてしまうと相続放棄はできなくなります。
2-2.一定期間内に売却すると譲渡所得税の特例が受けられる
後ほど解説するように、土地を売却した場合などには譲渡所得税の対象となります。
この譲渡所得税にはさまざまな特例があり、相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に土地を譲渡した場合にはその土地の取得にかかった分の相続税を取得費に加算できる特例の適用が可能です。
そのため次のすべてに当てはまる場合には、相続開始の翌日から3年10ヶ月以内の売却を検討すると良いでしょう。
- その土地が相続で取得したものであること
- その土地の取得に相続税がかかっていること
- その土地の売却に譲渡所得税がかかりそうなこと
特例の適用を受けたい場合には、あらかじめ税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
2-3.小規模宅地等の特例を利用した土地の場合には税理士に相談する
小規模宅地の特例とは、相続税の計算上土地を最大8割減で評価できる特例です。相続税の大きな軽減につながる特例であるため、要件を満たす場合にはこの特例の適用を受けることとなるでしょう。
しかしこの特例の適用を受けた土地の売却には注意しなければなりません。なぜなら小規模宅地等の特例にはさまざまな要件があり、相続税の申告期限までその土地を有していることが要件となっている場合もあるためです。
また相続税の申告期限後の売却であっても、その売却対価が相続税を計算するうえでの評価額と比較して非常に高額である場合などには、そもそも評価方法に問題があったとして追徴が求められる可能性もあるでしょう。
そのため相続税の対象となった土地や相続税の計算にあたって小規模宅地等の特例の適用を受けた土地を売却する場合には、あらかじめ税理士へ相談することをおすすめします。
2-4.慌てて売ると安く買われてしまうリスクがある
相続した土地を売却する場合、相続税の納税資金を確保することが目的である場合もあるでしょう。この場合には、相続税の納税期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に間に合わせたいことかと思います。
しかし売り急いでいることを買い手が察すれば、不当に安い価格で買いたたかれてしまうかもしれません。
そこで信頼できる不動産会社から査定を受けることが非常に重要となります。正当な査定額を知っておけば、どの程度の価格までなら容認できるのか判断がしやすいためです。
そして査定を受ける際には、複数の不動産会社へ依頼すると良いでしょう。なぜなら複数の査定額を比べることで、適正な査定額を把握しやすくなるためです。
また査定額を比較することで、その物件の売却を得意とする不動産会社を見つけやすくなります。複数の不動産会社へ査定を依頼したい場合には、SREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご利用ください。
3.相続登記の基本の流れ

その土地が相続でもらったものである場合、手放す前にまず相続登記をすべきことは先ほど解説したとおりです。では相続登記はどのように進めれば良いのでしょうか?基本的な流れは次のとおりです。
- 相続する人を決める
- 必要書類を準備する
- 相続登記を申請する
3-1.相続する人を決める
はじめにその土地を相続する人を決めなければなりません。相続する人を決めるには主に次の2パターンが存在します。
- 遺言書に従う
- 遺産分割協議で決める
3-1-1.遺言書に従う
被相続人(亡くなった人)が遺言書を遺しており、その遺言書で土地の取得者を決めていた場合には原則としてその遺言書にしたがって土地の取得者が決まります。
3-1-2.遺産分割協議で決める
その土地の取得者を指定した遺言書などがない場合には、遺産分割協議で土地の取得者を決めます。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が必要であり、無事に合意ができたらその内容を遺産分割協議書に落とし込みます。
3-2.必要書類を準備する
相続登記には登記申請書のほか、被相続人の古い戸籍(「除籍謄本」や「原戸籍謄本」といいます)や遺産分割協議書などさまざまな書類が必要です。
また必要書類は状況によって異なる場合があり、これを自分で行おうとすれば多大な手間や時間を要してしまいます。そのため司法書士へ手続きを依頼することも検討すると良いでしょう。
3-3.相続登記を申請する
必要書類が揃ったら法務局へ申請します。申請には窓口へ持ち込む方法のほか、郵送やオンラインでも可能です。
4.要らない土地を手放す方法①:売却する
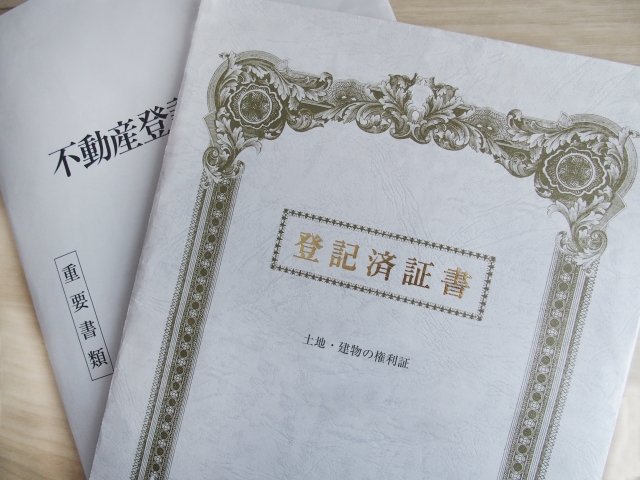
ここからは要らない土地を手放す5つの方法について解説します。まずは土地を売却することのメリットとデメリットを紹介しましょう。
実は自分では「このような土地では買い手がつかないだろう」と考えていても、買い手が見つかるケースは少なくありません。またこの方法は唯一、多少なりとも対価が得られる方法です。
そのため手放したい土地がある場合には、まず優先的に売却を検討すると良いでしょう。
しかし土地が売れるかどうか自分で判断することは容易ではありません。そこでまずは不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。
査定を依頼する際には「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。不動産会社はそれぞれエリアや物件種別(中古住宅、空き家、更地、マンションなど)によって得意分野が異なります。
そのため複数の不動産会社から査定を取ることで、その土地の売却に前向きとなってくれる不動産会社を見つけやすくなるでしょう。
4-1.メリット
売却を選択する最大のメリットは、対価が得られる可能性がある点です。売却以外の方法を選択した場合には、無償であるもしくは手放すために対価を支払わなければなりません。
4-2.デメリットと注意点
売却を選択する際のデメリットと注意点は主に次のとおりです。
- 譲渡所得税の対象となる
- 買い手が見つかるとは限らない
- 適正価格かどうかの判断が難しい
4-2-1.譲渡所得税の対象となる
1つ目のデメリットは譲渡所得税(と住民税)がかかる可能性がある点です。
ただし譲渡所得税は土地を売って得た「儲け」に対してかかる税金であるため、土地を売ったからといって必ずしも譲渡所得税がかかるわけではありません。そのため次の式で算定する課税譲渡所得金額が0以下となる場合には譲渡所得税の納税は不要です。
- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)
それぞれの要素の概要は次のとおりです。
- 収入金額:土地の売却で得た対価。
- 取得費:その土地を取得するためにかかった購入代金など。取得費が不明な場合には収入金額の5%で計算する。
- 譲渡費用:その土地を売却するのにかかった仲介手数料、印紙税、土地上にあった建物の解体費用など。
また譲渡所得税には次のようなさまざまな特別控除があります。要件を満たして確定申告をすればこれらの金額を課税譲渡所得金額から差し引くことが可能です。
- マイホームを売ったときの特別控除:3,000万円
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除:3,000万円
- 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除:1,000万円
そのため要らない土地を手放すために売却したような場合には、結果的に譲渡所得税がかからないことも少なくないでしょう。
一方で特別控除を差し引いてもなお課税譲渡所得金額が発生する場合には、土地の所有期間に応じて次の税率を乗じ譲渡所得税と住民税を計算します。
| 譲渡した年の1月1日時点での所有期間 | 税率(令和19年分まで) |
| 5年超 | 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
| 5年以下 | 39.63%(所得税30.63%、住民税9%) |
なお譲渡所得税は国などが計算して納付書が届くようなものではなく、土地を売却した翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。譲渡所得税額が発生する場合や特別控除の適用を受けたい場合には、必ず期限内に申告を行ってください。
4-2-2.買い手が見つかるとは限らない
土地を売って手放したくても買い手がいなければ手放すことはできません。土地は必要な人にとっては非常に有用なものである一方で、要らない人が買っても管理に手間がかかってしまうだけだからです。
そのため立地や状況などから見て土地が売りにくそうである場合には、他の方法を取ることも検討しておく必要があるでしょう。
4-2-3.適正価格かどうかの判断が難しい
土地の価格は原則として相対的に決まります。
同じ土地であっても、たとえば自分の家の隣に長男一家の家を建てたいと考えている人にとっては価値が高い一方で、その地にゆかりのない人にとってはたとえ相場より安くても要らない場合もあるでしょう。また同じ土地は2つとして存在せず、仮に近隣で土地の売却事例があったとしてもその土地とまったく同じ単価で売れる保証などありません。
このような事情から、仮に購入希望者から「〇〇円なら買いたい」などといわれてもそれが適正であるかどうか判断することは容易ではないでしょう。土地を売る際にこの「値決め」が非常に難しいといえます。
そこでおすすめしたいのが「おうちクラベル」のご利用です。おうちクラベルでは、複数の優良な不動産会社にまとめて査定を依頼することができます。複数社の査定額を比較することでその土地の適性額を知ることができるでしょう。
また高い査定額を付けた不動産会社は、その土地の売却にノウハウがある可能性があります。そのため査定額や査定額への説明などを比較検討することでその土地の売却に強い不動産会社を見つけやすくなるでしょう。
5.要らない土地を手放す方法②:寄付する

土地を手放したい場合に検討したい2つ目の方法は寄付をすることです。寄付とは、対価を得ずに土地を自治体や団体、企業などへ引き渡すことを指します。
寄付のメリットとデメリットはそれぞれ次のとおりです。
5-1.メリット
土地を手放したい場合、寄付をする主なメリットは次のとおりです。
- 土地を有効活用してもらいやすい
- 税制上のメリットが受けられる可能性がある
5-1-1.土地を有効活用してもらいやすい
土地を手放したいとはいえ、その土地に愛着がある場合などには有効に活用して欲しいと望む場合もあるでしょう。信頼できる寄付先に事前に希望を伝えたうえで納得して寄付が受け入れられた場合には、有効活用をしてもらえる可能性が高くなります。
ただし土地の用途についてあまりに厳しい希望を出した場合には、寄付自体を断られる可能性が高くなるでしょう。
5-1-2.税制上のメリットが受けられる可能性がある
寄付先が国や地方公共団体である場合には寄付金控除の対象となり、税制上のメリットが受けられる可能性があります。ただし控除を受けるためには所定の手続きが必要であるため、あらかじめ管轄の税務署か税理士へ相談しておくと良いでしょう。
5-2.デメリットと注意点
寄付によって不要な土地を手放す場合の主なデメリットと注意点は次のとおりです。
- 土地を無理に押し付けることはできない
- みなし譲渡所得の対象となる可能性がある
5-2-1.土地を無理に押し付けることはできない
たとえ相手が国や地方公共団体であったとしても、相手が要らないと考えている土地を無理に押し付けることはできません。
預金などとは異なり、土地は持っているだけでも管理に手間やコストがかかります。そのため資産価値が高く換金できる可能性のある土地やちょうど自治体が必要としている土地などでない限り断られる可能性が高いでしょう。
5-2-2.みなし譲渡所得の対象となる可能性がある
土地の寄付先が法人であれば、みなし譲渡所得税の対象となる可能性があります。みなし譲渡所得税とは、時価で土地の譲渡があったものとみなされて譲渡所得税の対象となる制度です。
ただし寄付先が国や自治体、一定の要件を満たした公益法人等である場合には、例外的にみなし譲渡所得税の対象から外れます。
無償で土地を寄付したにもかかわらず税金がかかるという点に納得がいかないと感じる方も少なくないでしょう。しかしこのような規程が存在する以上、仮に納税をしなければ無申告加算税などのペナルティの対象となってしまいます。
「譲渡所得税がかかると知っていれば寄付などしなかったのに」と後悔してしまわないためにも、土地の寄付をする場合にはあらかじめ管轄の税務署か税理士へ相談しておいた方が良いでしょう。
6.要らない土地を手放す方法③:贈与する
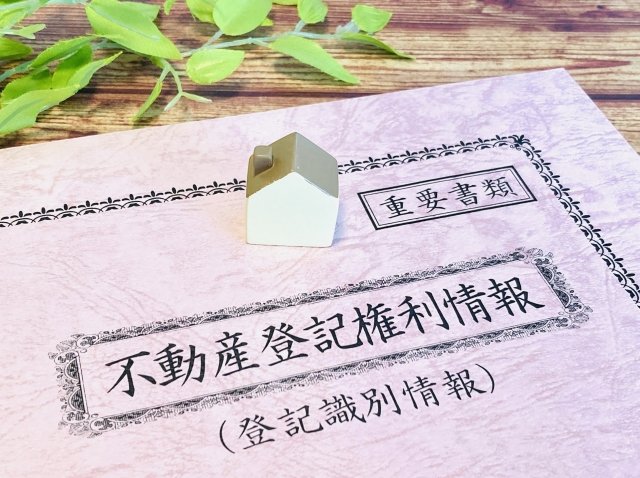
土地を手放す方法の3つ目は贈与をすることです。ここでは一つ前で解説した「寄付」と比較するために、個人に対して無償で土地を渡すことを「贈与」とします。
贈与によって土地を手放す方法のメリットとデメリットはそれぞれ次のとおりです。
6-1.メリット
要らない土地を贈与によって手放す主なメリットは、寄付と同じく土地を有効活用してもらいやすい点です。たとえば隣地所有者が自宅を増築したいと考えているタイミングで隣地所有者へ土地を贈与すれば、非常に感謝してもらえることでしょう。
6-2.デメリットと注意点
贈与によって土地を手放した場合には、土地をもらった人に対して贈与税がかかります。贈与税はある人が1月1日から12月31日までに受けた贈与をトータルし、110万円を控除した残額に対して課税されます。
贈与税は贈与を受けた側が支払うべき税金であり、贈与した側にかかるものではありません。しかし贈与をした相手と後にトラブルとならないよう、贈与税の対象となる可能性があることをあらかじめ教えてあげると親切でしょう。
7.要らない土地を手放す方法④:相続放棄する

手放したい土地を自分が購入したのではなく、被相続人(亡くなった人)が保有していた場合には相続放棄が選択肢の1つとなります。くわしく解説していきましょう。
7-1.相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述をすることによってはじめから相続人ではなかったこととする手続きです。相続放棄をするとプラスの財産が一切相続できなくなる代わりに、マイナスの財産も承継せずに済むこととなります。そのため被相続人に借金が多くある場合などに利用されることが多いでしょう。
また特に相続したい財産がないのであれば、要らない土地を引き継がないために相続放棄することも選択肢の1つとなります。
7-2.相続放棄の注意点
相続放棄には注意点が少なくありません。主な注意点は次のとおりです。
7-2-1.他の財産も一切相続できなくなる
相続放棄は財産ごとにできるものではありません。たとえば「この土地だけを放棄して自宅不動産は相続する」ということや「借金と要らない土地だけを放棄して預貯金は相続する」などということは不可能です。
つまり相続放棄をすれば遺産である要らない土地を手放すことができる一方で、他のすべての遺産も相続できなくなるということです。相続放棄をする際にはこの点をよく理解したうえで行いましょう。
7-2-2.原則として相続開始後3ヶ月以内に行う必要がある
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として被相続人の死亡を知った時点です(前順位の相続人が相続放棄をしたことで順位が繰り上がった相続人となった場合などには例外があります)。
相続が起きてからの3ヶ月間は慌ただしく、あっという間に過ぎてしまうことでしょう。
そのため相続放棄を検討している場合には、できるだけ早期に取り掛かることが必要です。
7-2-3.被相続人の兄弟姉妹などにまで影響することがある
相続人には、次の順位が存在します。
- 第一順位:子どもなどの直系卑属(自分より後の世代で、直通する系統の親族。子や孫、ひ孫など。)
- 第二順位:両親などの直系尊属(自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。父母・祖父母など。)
- 第三順位:兄弟姉妹など
なお配偶者はこれとは別枠で、これらの人と一緒に相続人となります。そして前順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人が繰り上がって相続人となります。
そのため相続人の状況によっては、子どもが全員要らない土地を手放すために相続放棄をした結果、被相続人の両親や兄弟姉妹などにまで影響が及ぶ可能性があるということです。
7-3.相続放棄の手続き方法
相続放棄をするには、単に他の相続人などに宣言するのみでは足りず家庭裁判所へ申述しなければなりません。申述のためには相続放棄の申述書のほか、戸籍謄本などが必要です。
手続き方法や相続放棄の効果などについてより詳しく知りたい場合には、司法書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
8.要らない土地を手放す方法⑤:相続土地国庫帰属制度を利用する

令和5年(2023年)4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。これにより、不要な土地を手放す方法に新たな選択肢ができたこととなります。制度の概要は次のとおりです。
8-1.相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した「要らない土地」を国に帰属させることができる制度です。施行日以後に相続で取得した土地のみならず過去に相続で取得した土地であっても対象となります。
ただしこの制度を使って国庫に帰属させた土地を管理するのに要する費用の原資は税金です。そのため相続土地国庫帰属制度を使って国庫帰属させられる土地には一定の条件が定められているほか、10年分の管理費相当の負担金を納付しなければなりません。
8-2.相続土地国庫帰属制度が使える土地・使えない土地
相続土地国庫帰属制度はどのような土地でも使えるわけではありません。
まずこの制度が使えるのは、相続で取得した土地のみです。原則として自分で買った土地や贈与でもらった土地などには適用できません。
また次の土地に対しては相続土地国庫帰属制度が適用できず、申請しても却下されるか不承認となります。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
つまり相続土地国庫帰属制度によって国に引き取ってもらえるのは特に問題のない更地のみであるということです。特に「その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地」にどのような土地が該当するのかは、今後事例の蓄積が待たれるところでしょう。
8-3.相続土地国庫帰属制度と相続放棄の主な違い
相続土地国庫帰属と相続放棄との最大の違いは、他の遺産の相続に影響するかどうかです。
先ほど解説した相続放棄では、特定の土地だけを手放して他の遺産を相続することなどはできませんでした。一方相続土地国庫帰属制度では「要らない土地」だけをピンポイントで手放すことが可能です。
また相続土地国庫帰属の利用には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」などの期限はありません。そのためたとえば10年以上前に相続した土地であっても、相続土地国庫帰属制度の対象となります。
8-4.相続土地国庫帰属制度利用の流れ
相続土地国庫帰属制度を利用するための基本の流れは次のとおりです。
- 国庫帰属の承認申請と審査手数料の納付をする
- 法務局担当官による書面審査がされる
- 法務局担当官による実地調査がされる
- 土地の国庫帰属が承認される
- 承認通知から30日以内に負担金を納付する
- 移転登記をして土地が国庫に帰属する
相続土地国庫帰属制度についてより詳細に知りたい場合には、管轄の法務局のほか司法書士や行政書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
9.【ケース別】要らない土地を手放す方法

ここまで要らない土地を手放したい場合に活用できる5つの方法を解説しました。最後に、これらのうちどの方法が適切であるか、ケースごとにまとめて紹介します。
9-1.不動産の市場価値がある場合
手放したい土地に市場価値がある場合には、まず売却を検討することをおすすめします。なぜなら他の方法では対価が得られないばかりか、費用や税金がかかる可能性さえあるためです。
しかし市場価値があるかどうか自分で判断することは容易ではないでしょう。そこでおすすめなのが「おうちクラベル」のご利用です。
おうちクラベルとは、60秒入力で利用できる不動産一括査定サイトです。おうちクラベルをご利用頂くことで、複数の優良な不動産会社へまとめて査定を依頼することが可能となります。
複数社に査定を依頼することで売却の見込みがあるかどうかを知ることができるほか、市場価値を確認することができるでしょう。またその中から信頼できる不動産会社を選び土地の売却を依頼することも可能です。
9-2.不動産の価値は低いが活用してくれそうな人がいる場合
手放したい土地の価値が低く買い手が見つかる見込みは低い一方で、有効に活用してくれそうな相手がいる場合にはその相手への贈与や寄付が選択肢となります。
隣地の所有者や土地が所在する自治体に問い合わせてみれば贈与や寄付を受け入れてもらえる場合もあるでしょう。
9-3.価値が低くもらい手も見つからない場合
土地の価値が低くもらい手も見つからない場合には、相続土地国庫帰属制度もしくは相続放棄を検討することとなります。ただしそれぞれ要件が定められているため、要件を確認したうえで手続きを進めることが必要です。
10.まとめ

土地を手放したい場合の選択肢について解説しました。手放したい土地がある場合にはまず売却を検討し、次に寄付または贈与、最後に相続放棄や相続土地国庫帰属制度の利用を検討すると良いでしょう。
そして土地の資産価値や売却見込みを知りたい場合には不動産会社へ査定を依頼することをおすすめします。また不動産会社にはそれぞれエリアや物件種別に応じて得意分野が異なる場合があるため、査定の依頼は複数の不動産に行うと良いでしょう。
複数の不動産会社に査定を依頼したい場合にはSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご利用ください。おうちクラベルでは、60秒入力で複数の優良な不動産会社へ査定を依頼することが可能です。
土地の査定額や土地の売却見込みを知ったうえで信頼できる不動産会社へ土地の売却を依頼しましょう。












