さまざまな事情によって、相続した不動産を売りたい場合もあると思います。
では、相続した不動産の売却をしたい場合、どのような手順で進めていくとよいでしょうか?
また、どのような点に注意するとよいでしょうか?
今回は、相続した不動産の売却をする流れや注意点、売却でかかる税金などについて詳しく解説します。
相続した不動産の売却をする3つの方法

相続した不動産の売却をする方法には、次の3つがあります。
- 1人が相続して売却する
- 1人の代表者名義にして不動産を売却し売却対価を分ける
- 共有名義で相続して売却する
1人が相続して売却する
1つ目は、相続人の1人が不動産を相続して、その者が不動産を売却する方法です。
この方法が相続した不動産の売却する原則的な方法であり、もっともシンプルな方法でもあります。
1人の代表者名義にして不動産を売却し売却対価を分ける
2つ目は、相続人の1人がいったん不動産を相続して、その売却対価を分ける方法です。
このような相続の方法を、「換価分割」といいます。
不動産の換価分割をする際は、その売却対価を分ける際に贈与であると見られないよう、遺産分割協議書の書き方を工夫しなければなりません。
換価分割にはほかにも注意点が少なくないため、この方法をとることが適切であるかどうか、あらかじめ税理士などの専門家へよく相談することをおすすめします。
共有名義で相続して売却する
3つ目は、共有名義不動産を相続し、共有者全員で売却する方法です。
たとえば、相続人であるA氏、B氏、C氏の3名が不動産を1/3ずつの共有で相続し、売却対価も1/3ずつで分ける方法がこれに該当します。
換価分割をするのであれば、この方法の方がシンプルであるといえます。
ただし、売却にあたって共有者全員の意見を合致させる必要があるため、たとえば「A氏とB氏は3,500万円以下では売りたくないと考えている一方で、C氏は3,200万円でもよいからできるだけ早く売りたい」など、売却に関する意見がまとまらずトラブルとなる可能性があります。
相続した不動産の売却をする流れ・手順
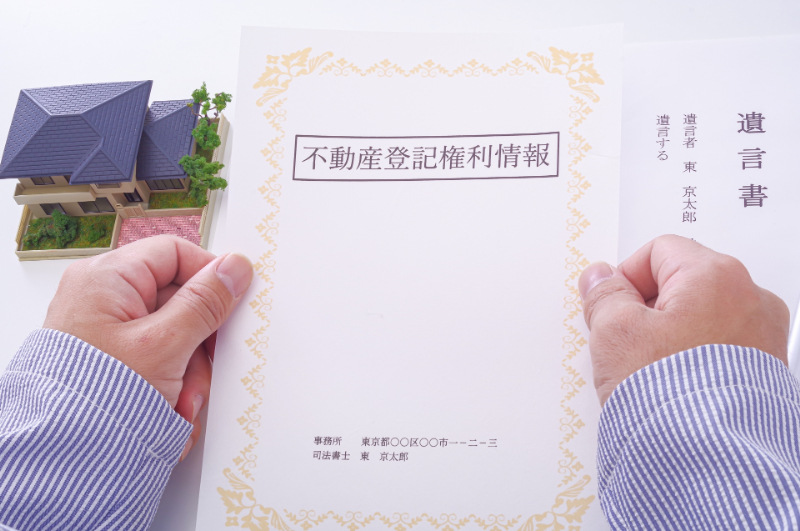
相続した不動産の売却をする際は、どのような流れや手順で進めるとよいでしょうか?
一般的な流れは、次のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 遺産の全容と相続人を確認する
- 遺産分割協議をする
- 相続登記を申請する
- 不動産会社に査定の依頼をする
- 売却を依頼する不動産会社を選定する
- 不動産会社と媒介契約を締結する
- 相続した不動産を売りに出す
- 売買契約を締結する
- 不動産を引き渡す
- 必要に応じて確定申告をする
なお、ここからは、不動産を相続人の1人が相続して売却することを前提として解説します。
遺言書の有無を確認する
相続が起きたら、はじめに亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺言書の有無を確認します。
遺言書があるかどうかによって、遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)が必要であるかどうかが異なるためです。
遺言書の有無は、次の方法などで確認できます。
- 被相続人の自宅内を探す
- 一定の書類を揃えて最寄りの公証役場で調べてもらう
- 一定の書類を揃えて最寄りの法務局で調べてもらう
- 生前に付き合いのあった専門家へ問い合わせる
有効な遺言書があった場合は、原則として遺産分割協議をするまでもなく遺言書で指定のあった者が不動産を取得することとなります。
なお、ここでは遺言書がなかったものとして解説を進めます。
遺産の全容と相続人を確認する
次に、遺産の全容と相続人を確認します。
遺産の全容を確認すべき理由は、遺産の全容がわかっていないと遺産分割協議を行うことが難しいためです。
判明した遺産は一覧表にまとめておくと、遺産分割協議の参考となります。
また、相続人を確認すべき理由は、相続人が1人でも漏れると遺産分割協議が無効になってしまうためです。
遺産や相続人を自分で確認することが難しい場合は、司法書士や行政書士に依頼して調べてもらうことも可能です。
遺産分割協議をする
遺産と相続人が確認できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の成立には、相続人全員による合意が必要です。
1人でも協議に納得しない相続人がいる場合や遺産分割協議の連絡を無視する相続人がいる場合は、弁護士へ相談して解決を図ることをおすすめします。
無事に遺産分割協議がまとまったら、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印で押印します。
相続登記を申請する
遺産分割協議がまとまったら、必要書類を揃えて相続登記を申請します。
相続登記の手続きや必要書類の収集は、司法書士へ依頼するとスムーズです。
不動産会社に査定の依頼をする
相続登記を申請したら、不動産会社に査定の依頼をします。
査定とは、不動産会社にその不動産の売却想定額を算定してもらう手続きです。
査定にはぜひ、「おうちクラベル」をご活用ください。
おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。
査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、その不動産の売却適正額が把握しやすくなります。
売却を依頼する不動産会社を選定する
査定結果が出揃ったら、売却の依頼をする不動産会社を選定します。
不動産会社は査定額の高さだけで決めるのではなく、査定額への説明や担当者の誠実さなどを総合的に踏まえて決めることをおすすめします。
なぜなら、査定額はあくまでもその不動産会社が考える売却予想額であり、必ずしもその価格で不動産の売却を成功させる保証ではないためです。
不動産会社と媒介契約を締結する
不動産会社を選定したら、その不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には次の3種類があります。
状況や希望に合った媒介契約を選択してください。
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 他の不動産会社へ重ねての依頼 | 不可 | 不可 | 可 |
| 自己発見取引 (自分で買主を見つけて売却すること) | 不可 | 可 | 可 |
| 指定流通機構(レインズ)への登録義務 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | 義務なし |
| 報告頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 指定なし |
どの媒介契約がよいと一概にいえるものではないものの、不動産会社に販売活動に力を入れてほしい場合は「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」を選ぶことをおすすめします。
なぜなら、これらは重ねて他社と契約することができないことから、不動産会社に責任をもって販売活動をしてもらいやすくなるためです。
相続した不動産を売りに出す
媒介契約を締結したら、不動産を売りに出します。
不動産を売り出す際は、売主側の希望売却価格である「売出価格」を決めます。
売出価格の設定が売却の成否を決めるといっても過言ではないため、不動産会社の担当者とよく相談したうえで決めるようにしてください。
売買契約を締結する
買主が不動産の購入を決めたら、売買契約を締結します。
売買契約の締結時には、買主から売主に対して売買金額の5%から10%程度の手付金が交付されることが一般的です。
不動産を引き渡す
あらかじめ取り決めた日に、不動産を引き渡します。
この日には、次のことを同時に行うことが一般的です。
- 買主のローンの実行
- 買主から売主へ売買代金全額(手付金を除く)の支払い
- 売主から買主へ不動産のカギなどの引き渡し
- 売主から買主へ不動産の名義を変えるための書類への署名押印
その後、立ち会った司法書士が法務局へ登記申請し、不動産の名義が買主へと変わります。
必要に応じて確定申告をする
不動産を売却して利益が出たら、その利益に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は自分で計算し、確定申告をしなければなりません。
譲渡所得税の申告期限は、売却の翌年2月16日から3月15日までです。
相続した不動産の売却でかかる主な税金

相続した不動産の売却では、さまざまな税金がかかります。
主にかかる税金は次のとおりです。
- 相続税
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税
相続税
相続税とは、遺産などに対してかかる税金です。
不動産も相続税の対象であり、相続が起きてからすぐに売却したからといって相続税の課税対象から外れるわけではありません。
ただし、相続税には次の基礎控除額が設けられています。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
そのため、相続税の対象となる遺産や過去の一定の贈与がこの基礎控除額以下である場合は、相続税はかかりません。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書などの文書にかかる税金です。
不動産の売買契約書も印紙税の課税対象であり、税額はそれぞれ次のとおりです。
2024年3月31日までに作成する契約書には、軽減税率が適用されます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 (2024年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記などに対してかかる税金です。
売買による名義変更にも登録免許税はかかるものの、これは買主が負担することが一般的です。
一方、相続登記にかかる登録免許税は、売主が負担します。
相続登記にかかる登録免許税は、次の式で算定します。
- 登録免許税=その家の固定資産税評価額×4/1,000
なお、相続登記手続きを司法書士へ依頼する場合、8万円から15万円程度の報酬が別途かかります。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却して得る利益に対してかかる税金です。
譲渡所得税は次の式で算定します。
- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率
譲渡所得税は計算要素が多いうえ、税額を大きく左右する特別控除も数多く設けられているため、自分で正しく算定することは容易ではありません。
査定額がわかった段階で税理士などの専門家へ相談し、譲渡所得税を試算してもらっておくとよいでしょう。
相続した不動産の売却で使える譲渡所得税の特例

相続した不動産の売却にかかる譲渡所得税では、次の特例が使える可能性があります。
- 取得費加算の特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
取得費加算の特例
「取得費加算の特例」とは、その不動産を相続するために売主が支払った相続税を、譲渡所得税の計算する際の「取得費」に加算することができる特例です。
取得費に加算することができる金額は、次の式で算定します。
- 取得費に加算する相続税額=売主が支払った相続税額×譲渡した不動産の相続税評価額÷売主の取得財産の価格等
計算式は複雑に見えるものの、売主が支払った相続税のうちその不動産にかかった相続税を、按分して計算しています。
この特例の適用を受けるには、相続した不動産を相続してから3年10か月以内に売却しなければなりません。
参照元:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(国税庁)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得税の3,000万円特別控除」とは、相続で空き家となった被相続人の元自宅を売る場合に、最大3,000万円の特別控除が受けられる特例です。
控除できる金額が大きいため、この特例の適用を受けることで譲渡所得税がゼロとなることも少なくありません。
ただし、この特例の適用を受けるためには、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに不動産を売却することが必要です。
参照元:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
ほかにもさまざまな要件が設けられているため、相続した不動産の売却をする際は査定額が分かった時点で税理士などの専門家へ相談のうえ、要件を満たすかどうかあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。
相続した不動産を売る際の注意点

相続した不動産の売却をする際は、次の点に注意が必要です。
- 故人名義のままでは売却ができない
- 査定は複数の不動産会社へ依頼する
- 売却対価を分ける場合は贈与にならないよう注意する
故人名義のままでは売却ができない
先ほども解説したように、不動産は故人名義のままで売却することはできません。
相続した不動産の売却をするには、売却に先立って相続登記をしなければなりません。
たとえ遺産分割協議がスムーズにまとまったとしても、書類を用意する期間を含めると相続登記の完了までには1か月から2か月程度の期間がかかります。
そのため、相続した不動産を売る際は早期に相続登記に取りかかることをおすすめします。
査定は複数の不動産会社へ依頼する
相続した不動産の売却をする際は、複数の不動産会社に査定の依頼をするようにしてください。
査定額が不動産会社によって異なることは珍しくなく、1社だけから査定を受けた場合はその査定額が適正であるかどうか判断することが難しいためです。
複数社から査定を受けることでその不動産の売却適正額が把握しやすくなるほか、その不動産をよりよい条件で売ってくれる不動産会社を見つけやすくなります。
しかし、自分で複数の不動産会社に査定の依頼をすることには、多大な手間と時間を要します。
そのような際は、ぜひ「おうちクラベル」をご活用ください。
おうちクラベルでは、査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、自分で1社1社を回る必要はありません。
売却対価を分ける場合は贈与にならないよう注意する
相続人のうち1人の代表者名義にして不動産を売却し、売却対価を分ける手法をとる場合は、売却対価の交付が贈与であると疑われないよう対策をとることが必要です。
税務当局から贈与であると判断されると、交付した売却対価に対して高額な贈与税が課される可能性があるためです。
贈与であるとの疑いをもたれないためには、遺産分割協議書に換価分割をする目的で代表者が不動産を取得することを明記することがポイントです。
遺産分割協議書を作成する際は、税理士などの専門家へ確認してもらうことをおすすめします。
まとめ
相続した不動産の売却をする流れやかかる費用、税金などについて解説しました。
相続した不動産の売却をする際は、まず相続登記をすべきことに注意しなければなりません。
相続登記の完了までには1か月から2か月程度の時間がかかるため、早めに取り掛かることがポイントです。
そして、相続した不動産をよりよい条件で売るには、ぜひ「おうちクラベル」をご活用ください。
おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。
査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、査定額や対応などを比較することで、その不動産をよりよい条件で売却してくれる不動産会社を見つけやすくなります。











